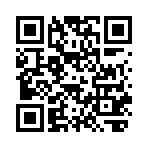スポンサーサイト
今からの受験対策法!
2012年11月16日
さて、受験日が刻々と迫って参りました。
焦っている人も多いことでしょう。
さて、本日は今からでも点数を伸ばす方法をお教えします。
1.まず受験校の過去問を解きます。
大分前に既に解いた事のある人は、もう一度忘れた頃の過去問を解きます。
2.点数が取れそうな部分を探します。
すぐに点数になりやすいのは数学(算数)です。
特に得点が低い人は、簡単な計算問題などができているか確認しましょう。
難しすぎる問題は、ほとんどの受験生が解けません。
そんな所で悩むより、すぐにどうにかなりそうな部分を中心に学習しましょう。
100点をとる必要なんてないのです。
1教科くらい0点をとっても、他の教科が90点なら、受かるかもしれませんね。
逆に漢字の読み書きなどは捨てる勇気も必要です。
単純な計算問題と同じように、一見簡単に点数になりそうに見える部分ですが、
どの漢字が出題されるか分かりません。
たった1点をとるために、30も40も漢字を覚える努力をしなければなりません。
余裕がなければまずは他の部分で点が取れないか探しましょう。
山をはるのではなく「確実に取れるところを落とさないようにする」と考えてください。
3.得意な分野を伸ばすか、苦手な分野を克服するか。
得意な分野なのにその部分で点数が取れていない場合はラッキーです。
まずは得意な分野で点数を取れるようにもう一度見直しましょう。
得意な分野はきちんとできていて、簡単な問題も全てできている、という優秀な方は、
点数が取れていない分野に着目しましょう。
4.焦らず一つ一つ。
当然ですが、焦ってしまうと「あれもしないと、これもしないと」と、
バラバラと手をつけてしまって、中々身になりません。
しっかり一つ一つ点数を取れるようにしていくことが重要です。
どの教科も平均的に解けなければならないような資格試験とは違います。
全教科の中で1点でも多く取れればいいのです。
5.たくさんのテキストに手を付けるな。
各教科で受験対策になりそうな1冊に絞り、信じて勉強しましょう。
厚いテキストは中々終わらず焦る一方です。
練習問題がしっかりある、薄いテキストを1冊終わらせる気持ちでやりましょう。
多くのテキストをやるより、1冊を繰り返しやる方が身になります。
6.受験日までの計画を立てる
上記を踏まえ、今から勉強すべき事を書き出して見ましょう。
そして、その勉強をどのようにやっていくのかを計画しましょう。
毎日やらないと忘れるようなものは、ベースとして1日○分間などと決めます。
あとは計画通りにやっていくだけ。
どうしても躓いた場合は早めに計画を変更しましょう。
とにかく「点が取れるものを把握して、無駄に落とさない」というのが、直前の課題ですよ。
焦っている人も多いことでしょう。
さて、本日は今からでも点数を伸ばす方法をお教えします。
1.まず受験校の過去問を解きます。
大分前に既に解いた事のある人は、もう一度忘れた頃の過去問を解きます。
2.点数が取れそうな部分を探します。
すぐに点数になりやすいのは数学(算数)です。
特に得点が低い人は、簡単な計算問題などができているか確認しましょう。
難しすぎる問題は、ほとんどの受験生が解けません。
そんな所で悩むより、すぐにどうにかなりそうな部分を中心に学習しましょう。
100点をとる必要なんてないのです。
1教科くらい0点をとっても、他の教科が90点なら、受かるかもしれませんね。
逆に漢字の読み書きなどは捨てる勇気も必要です。
単純な計算問題と同じように、一見簡単に点数になりそうに見える部分ですが、
どの漢字が出題されるか分かりません。
たった1点をとるために、30も40も漢字を覚える努力をしなければなりません。
余裕がなければまずは他の部分で点が取れないか探しましょう。
山をはるのではなく「確実に取れるところを落とさないようにする」と考えてください。
3.得意な分野を伸ばすか、苦手な分野を克服するか。
得意な分野なのにその部分で点数が取れていない場合はラッキーです。
まずは得意な分野で点数を取れるようにもう一度見直しましょう。
得意な分野はきちんとできていて、簡単な問題も全てできている、という優秀な方は、
点数が取れていない分野に着目しましょう。
4.焦らず一つ一つ。
当然ですが、焦ってしまうと「あれもしないと、これもしないと」と、
バラバラと手をつけてしまって、中々身になりません。
しっかり一つ一つ点数を取れるようにしていくことが重要です。
どの教科も平均的に解けなければならないような資格試験とは違います。
全教科の中で1点でも多く取れればいいのです。
5.たくさんのテキストに手を付けるな。
各教科で受験対策になりそうな1冊に絞り、信じて勉強しましょう。
厚いテキストは中々終わらず焦る一方です。
練習問題がしっかりある、薄いテキストを1冊終わらせる気持ちでやりましょう。
多くのテキストをやるより、1冊を繰り返しやる方が身になります。
6.受験日までの計画を立てる
上記を踏まえ、今から勉強すべき事を書き出して見ましょう。
そして、その勉強をどのようにやっていくのかを計画しましょう。
毎日やらないと忘れるようなものは、ベースとして1日○分間などと決めます。
あとは計画通りにやっていくだけ。
どうしても躓いた場合は早めに計画を変更しましょう。
とにかく「点が取れるものを把握して、無駄に落とさない」というのが、直前の課題ですよ。
高校の選び方2
2012年11月13日
さて以前、高校の選び方は「自分(子ども)に合った学校を選ぶ」というお話をしました。
では、その学校のことを調べましょう。
調べ方として、その学校のホームページを見るのは基本として、
そこに通う生徒の生の声を聞きましょう。
パンフレットやオフィシャルのホームページでは、良いことしか書いていないのは当たり前ですし、具体的にどんな雰囲気なのかは分かりませんよね。
このようなページから情報を仕入れることができる時代です。
2ちゃんねる系なので、全てを鵜呑みにしないことが重要ですが。
なんとなく、そこの学校の雰囲気は分かるでしょう。
「課外が多すぎる」
「課外がほとんどない」
「生徒の自主性に任せている」
「宿題・予習が多すぎる」
「体育祭が盛り上がる」
「~部が強い」
今は色んな所にたくさんの掲示板等がありますので、是非覗いてみてください。
まぁ、直接聞ける先輩がいればそれが一番いいですが。
では、その学校のことを調べましょう。
調べ方として、その学校のホームページを見るのは基本として、
そこに通う生徒の生の声を聞きましょう。
パンフレットやオフィシャルのホームページでは、良いことしか書いていないのは当たり前ですし、具体的にどんな雰囲気なのかは分かりませんよね。
このようなページから情報を仕入れることができる時代です。
2ちゃんねる系なので、全てを鵜呑みにしないことが重要ですが。
なんとなく、そこの学校の雰囲気は分かるでしょう。
「課外が多すぎる」
「課外がほとんどない」
「生徒の自主性に任せている」
「宿題・予習が多すぎる」
「体育祭が盛り上がる」
「~部が強い」
今は色んな所にたくさんの掲示板等がありますので、是非覗いてみてください。
まぁ、直接聞ける先輩がいればそれが一番いいですが。
距離で高校を選ぶ。
2012年11月07日
イイと思います。
前にも書いたように、お子様の性格と合った学校であれば。
無理して遠い高校に行くと、通学時間のロスが出ます。
近くの高校に行けば、通学時間を勉強やスポーツに充てることができます。
私は通学に片道50分くらいかかっていました。
一日100分の間にどれだけの英単語が覚えられたでしょう(笑)
バス通学でしたから、車内で単語を覚えていましたが、全く集中できませんでした。
宿題と予習に追われる毎日でした。
朝課外があり、夕課外があり、帰ったら宿題に予習。
それだけで2時とか3時。
後は寝るだけって。
疲れ果てます。。。
まぁ、私の高校が厳しすぎたのではありますが…。
ちなみに、福岡の高校です。
距離で選ぶなんて安易過ぎるという考えは捨ててください。
志望校決定の重要な要素の一つです。
「時は学なり」です。
前にも書いたように、お子様の性格と合った学校であれば。
無理して遠い高校に行くと、通学時間のロスが出ます。
近くの高校に行けば、通学時間を勉強やスポーツに充てることができます。
私は通学に片道50分くらいかかっていました。
一日100分の間にどれだけの英単語が覚えられたでしょう(笑)
バス通学でしたから、車内で単語を覚えていましたが、全く集中できませんでした。
宿題と予習に追われる毎日でした。
朝課外があり、夕課外があり、帰ったら宿題に予習。
それだけで2時とか3時。
後は寝るだけって。
疲れ果てます。。。
まぁ、私の高校が厳しすぎたのではありますが…。
ちなみに、福岡の高校です。
距離で選ぶなんて安易過ぎるという考えは捨ててください。
志望校決定の重要な要素の一つです。
「時は学なり」です。
内申点って何!?
2012年11月07日
内申書とか内申点という言葉を聞いたことがありますか?
高校受験ではなぜかこのような言葉が飛び交います。
「そんなことしたら内申点に響くよ」って、子どもを脅すこともあるかもしれません(笑)
意外と知らない人ばかりなので、詳しくご紹介したいと思います。
学校現場を知らない学習塾も間違った情報ばかりですのでご注意を。
さて、「内申に響く」って言葉。
これは「カミナリ様にヘソを取られる」と同じような意味であって、本当にそんなことはありません。
内申書は、正式には「調査書」と言います。
その子が今まで学校生活でどのような事をやってきたのか、学業の成績はどうだったのかを書いた書類で、学校から受験校に提出されます。
例えば、生徒会で○○を担当したとか、学級委員をしたとか、部活で良い成績を収めたとか。
イメージで言うと、通知表の生活面に書いてある文章のようなもの。
でも、悪い事は一切書きません。
だって、悪い事書いたら落とされるでしょ?
どんなにやんちゃな子だって、1つくらい良い事はありますから、どうにかこうにか良いことを書きまくるんですよ。
生徒会とか学級委員、中体連で優勝とか、他生徒とは違う特別大きな事をやったのであればプラス評価されますが、他はさほど差はないでしょう。
さて、内申点の前に、重要な数値「評定平均」の事を。
評定とは通知表の5・4・3・2・1のことです。
全学年、全教科の評定を平均したもの(ただし、単純平均ではないです)が、評定平均となります。
つまり、特に調査書に重きを置く学校を受験する場合は、卒業間際だけ頑張ってもダメです。
1年生からコンスタントに高い評定を取っておかなければなりません。
多くの場合は筆記試験を重視し、調査書は参考程度にされる場合が多いので、さほど気にする必要はありませんが、余りに悪い場合は注意しておく必要がありますね。
そして、調査書の文面と評定平均を総合して、受験校側の基準で点数化します。
これが内申点ということになるでしょう。
この内申点が影響してくるのは推薦入試です。
それと、一般入試での筆記試験の結果がボーダーラインギリギリの時です。
あまりにも本気で気にされるお母様方がいらっしゃいますが、
調査書には悪い事は書きませんから、あまり気にする必要はありません。
ですが、ボーダーギリギリしか点が取れない場合は、今までの評定を考慮に入れて受験校を決めた方が良いかもしれません。
ただし、受験校側の基準で決められることですから、一概に言えないことも事実です。
まずは筆記試験の点数を取ることに注力することですね。
高校受験ではなぜかこのような言葉が飛び交います。
「そんなことしたら内申点に響くよ」って、子どもを脅すこともあるかもしれません(笑)
意外と知らない人ばかりなので、詳しくご紹介したいと思います。
学校現場を知らない学習塾も間違った情報ばかりですのでご注意を。
さて、「内申に響く」って言葉。
これは「カミナリ様にヘソを取られる」と同じような意味であって、本当にそんなことはありません。
内申書は、正式には「調査書」と言います。
その子が今まで学校生活でどのような事をやってきたのか、学業の成績はどうだったのかを書いた書類で、学校から受験校に提出されます。
例えば、生徒会で○○を担当したとか、学級委員をしたとか、部活で良い成績を収めたとか。
イメージで言うと、通知表の生活面に書いてある文章のようなもの。
でも、悪い事は一切書きません。
だって、悪い事書いたら落とされるでしょ?
どんなにやんちゃな子だって、1つくらい良い事はありますから、どうにかこうにか良いことを書きまくるんですよ。
生徒会とか学級委員、中体連で優勝とか、他生徒とは違う特別大きな事をやったのであればプラス評価されますが、他はさほど差はないでしょう。
さて、内申点の前に、重要な数値「評定平均」の事を。
評定とは通知表の5・4・3・2・1のことです。
全学年、全教科の評定を平均したもの(ただし、単純平均ではないです)が、評定平均となります。
つまり、特に調査書に重きを置く学校を受験する場合は、卒業間際だけ頑張ってもダメです。
1年生からコンスタントに高い評定を取っておかなければなりません。
多くの場合は筆記試験を重視し、調査書は参考程度にされる場合が多いので、さほど気にする必要はありませんが、余りに悪い場合は注意しておく必要がありますね。
そして、調査書の文面と評定平均を総合して、受験校側の基準で点数化します。
これが内申点ということになるでしょう。
この内申点が影響してくるのは推薦入試です。
それと、一般入試での筆記試験の結果がボーダーラインギリギリの時です。
あまりにも本気で気にされるお母様方がいらっしゃいますが、
調査書には悪い事は書きませんから、あまり気にする必要はありません。
ですが、ボーダーギリギリしか点が取れない場合は、今までの評定を考慮に入れて受験校を決めた方が良いかもしれません。
ただし、受験校側の基準で決められることですから、一概に言えないことも事実です。
まずは筆記試験の点数を取ることに注力することですね。
正しい高校の選び方。
2012年11月07日
「君は熊高に行ける実力があるから、熊高を受けなさい」
こんな事を学習塾から言われることがあります。
そんな実力があるのはうらやましいですね(笑)
でも、本当に行きたい高校は熊高なのでしょうか?
学習塾は実績を作るために、偏差値の高い高校を受けさせようとする場合があるのです。
高校入学当初はみんな同じような成績なので、中学校ではトップクラスの成績だったのに、全く目立たなくなってしまった、という話はよく聞きます。
それでやる気をなくしたって人もいれば、逆にもっと頑張ろうという気になったという人もいます。
中には勉学に厳しい高校もあります。
強制的にさせられる勉強で嫌になった、疲れてしまったという人もいれば、あの高校に行ったから自分は頑張れたという人もいます。
不思議なことに、高校入学当初はみんな同じ成績だったのに、卒業時には雲泥の差が開きます。
ぜひ、貴方に(お子様に)合う高校を見つけてください!
性格をよく考えてください。
自由な校風だとだらけてしまう人もいれば、頑張れる人もいます。
スパルタが合っている人もいれば、合わない人もいます。
偏差値レベルが高い高校だから、偏差値の高い大学に行けるのではありません。
たとえ低い高校に行っても、自分で勉強を頑張れば東大にだって行けるのです。
普通科・進学科・特進科であれば、どこの大学に行くにも不利という事はありません。
逆に、偏差値の高い生徒が偏差値の低い高校に行くと、("ひいき"と言われるかもしれませんが)とても大切にしてくれることもあります。
良い大学に行ってくれれば、宣伝になるからです。
結局のところ、大学受験の勉強は自分でしなければなりません。
東大完全対策授業とか、熊大完全対策授業とか、特別な授業があるわけではないのです。
「高校に行って、貴方が(お子様が)何をするか」が大切なんです。
熊本であまり良くない風潮に、「どこの高校卒?」と聞くというのがあります。
どこの高校に行った、よりもその後どうしたのかが重要ですよ!
こんな事を学習塾から言われることがあります。
そんな実力があるのはうらやましいですね(笑)
でも、本当に行きたい高校は熊高なのでしょうか?
学習塾は実績を作るために、偏差値の高い高校を受けさせようとする場合があるのです。
高校入学当初はみんな同じような成績なので、中学校ではトップクラスの成績だったのに、全く目立たなくなってしまった、という話はよく聞きます。
それでやる気をなくしたって人もいれば、逆にもっと頑張ろうという気になったという人もいます。
中には勉学に厳しい高校もあります。
強制的にさせられる勉強で嫌になった、疲れてしまったという人もいれば、あの高校に行ったから自分は頑張れたという人もいます。
不思議なことに、高校入学当初はみんな同じ成績だったのに、卒業時には雲泥の差が開きます。
ぜひ、貴方に(お子様に)合う高校を見つけてください!
性格をよく考えてください。
自由な校風だとだらけてしまう人もいれば、頑張れる人もいます。
スパルタが合っている人もいれば、合わない人もいます。
偏差値レベルが高い高校だから、偏差値の高い大学に行けるのではありません。
たとえ低い高校に行っても、自分で勉強を頑張れば東大にだって行けるのです。
普通科・進学科・特進科であれば、どこの大学に行くにも不利という事はありません。
逆に、偏差値の高い生徒が偏差値の低い高校に行くと、("ひいき"と言われるかもしれませんが)とても大切にしてくれることもあります。
良い大学に行ってくれれば、宣伝になるからです。
結局のところ、大学受験の勉強は自分でしなければなりません。
東大完全対策授業とか、熊大完全対策授業とか、特別な授業があるわけではないのです。
「高校に行って、貴方が(お子様が)何をするか」が大切なんです。
熊本であまり良くない風潮に、「どこの高校卒?」と聞くというのがあります。
どこの高校に行った、よりもその後どうしたのかが重要ですよ!