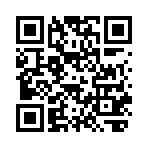スポンサーサイト
誤った科学実験方法に注意!
2017年10月11日
弊社では小学生を中心に、お子様に教えることが多いため、
正しい実験方法や解説を行うよう、日々勉強しています。
ユーチューバーが流行っている昨今、科学実験を取り入れた動画も多くなっておりますが、
誤った実験方法で行われているものが多々あり、いつか大事故が起きるのではと危惧しています。
「良い子の皆さんは真似しないで」と注釈が入っていればまだしも、
危険な行為だとも思わずに実施している例を見かけます。
科学に疎い方ならまだ分かるのですが、「プロ」と呼ばれている方にもこういった事例が多いことに驚きます。
この場を借りて、警鐘を鳴らしたいと思います。
イベントで行われるサイエンスショーや実験教室でも同じです。
今までの経験則だけで安全だと判断して行われている節があり、
おもしろさ・インパクトを求める余り、本当はやってはならない行為が目立ちます。
また、解説が科学的に正しくない事も多いです。
正しく言うと難し過ぎるのでアバウトに言う事は弊社でもありますが、
そういう意味ではなく、プロが全く間違ったことを言っていることがあるのです。
多少の認識不足は誰でもありますが、全く科学とかけ離れている場合があり、大変悲しい気分になります。
今回はとりあえず、最近気づいた危険な実験例を2つ挙げたいと思います。
■象の歯磨き粉
弊社のサイエンスショーでもよく行う実験です。
泡が高く噴き上がるのが大変インパクトがあり面白い実験ですが、噴き上がった瞬間の泡に触れるのは大変危険です。
海外発祥の実験で、実験方法だけが広まってしまったように思います。
過酸化水素が一瞬で分解されるために噴き上がると思われているようですが、
噴き上がる理由は「突沸」で、過酸化水素の分解はもう少しゆっくりです。
(過酸化水素は分解する時に発熱します)
事実、発泡の様子が2段階あります。
ヨウ化カリウムを入れた後、しばらくはゆっくりと泡が増えていきますが、ある瞬間に一気に膨らみます。
前半は過酸化水素の分解、後半は沸騰です。
噴き上がった泡はすぐに冷えますが、濃い過酸化水素(劇物)のままである可能性があります。
決して被ってはいけません。
随分前、イッテQで内村さんらが海外に行って火傷をする様子が放映されましたが、
日本のスタジオで行っていたら、放送事故だと思います。
もし泡に触れるのであれば、十分時間を置いてから、演示者が触れるだけにとどめるべきです。
十分時間を置いたものでも、泡に触れた指に刺激を感じることがあります。
ヨウ化カリウムが上手く混じっていない部分があって、分解されていない可能性もあります(未検証)。
■液体窒素
液体窒素の取り扱いや窒息の認識が誤っているものがあります。
液体窒素を水やお湯に入れると、液体窒素が急激に沸騰し、白い煙(湯気)が大量に発生します。
この白い煙の正体は、空気中に含まれる水蒸気が液体の水に戻ったものです。
つまり窒素だけではなく、空気が混じっているので、吸っても大丈夫だと言う方がいらっしゃいます。
しかし、酸素濃度が18%を切った気体を一吸いするだけで、窒息する場合があり、酷いと意識を失います。
通常の空気の酸素濃度は21%ですので、たった3%が窒素に置き換わっただけで危険性があるのです。
観客の方が深く呼吸をした場合は特に危険ですので、吸わせることは避けた方が良いと思います。
液体窒素で凍らせた食材を食べ、胃が破裂した例もあります。
ただでさえ凍傷の危険性があり、食材は何でもよい訳ではありません。
マシュマロを液体窒素に入れて食べるのは多く行われていますが、投入時間などを考えないと危険です。
弊社ではお子様に食べさせる行為は一切行っておりません。
危険な行為が目に余るので、記載させて頂きました。
正しい実験方法や解説を行うよう、日々勉強しています。
ユーチューバーが流行っている昨今、科学実験を取り入れた動画も多くなっておりますが、
誤った実験方法で行われているものが多々あり、いつか大事故が起きるのではと危惧しています。
「良い子の皆さんは真似しないで」と注釈が入っていればまだしも、
危険な行為だとも思わずに実施している例を見かけます。
科学に疎い方ならまだ分かるのですが、「プロ」と呼ばれている方にもこういった事例が多いことに驚きます。
この場を借りて、警鐘を鳴らしたいと思います。
イベントで行われるサイエンスショーや実験教室でも同じです。
今までの経験則だけで安全だと判断して行われている節があり、
おもしろさ・インパクトを求める余り、本当はやってはならない行為が目立ちます。
また、解説が科学的に正しくない事も多いです。
正しく言うと難し過ぎるのでアバウトに言う事は弊社でもありますが、
そういう意味ではなく、プロが全く間違ったことを言っていることがあるのです。
多少の認識不足は誰でもありますが、全く科学とかけ離れている場合があり、大変悲しい気分になります。
今回はとりあえず、最近気づいた危険な実験例を2つ挙げたいと思います。
■象の歯磨き粉
弊社のサイエンスショーでもよく行う実験です。
泡が高く噴き上がるのが大変インパクトがあり面白い実験ですが、噴き上がった瞬間の泡に触れるのは大変危険です。
海外発祥の実験で、実験方法だけが広まってしまったように思います。
過酸化水素が一瞬で分解されるために噴き上がると思われているようですが、
噴き上がる理由は「突沸」で、過酸化水素の分解はもう少しゆっくりです。
(過酸化水素は分解する時に発熱します)
事実、発泡の様子が2段階あります。
ヨウ化カリウムを入れた後、しばらくはゆっくりと泡が増えていきますが、ある瞬間に一気に膨らみます。
前半は過酸化水素の分解、後半は沸騰です。
噴き上がった泡はすぐに冷えますが、濃い過酸化水素(劇物)のままである可能性があります。
決して被ってはいけません。
随分前、イッテQで内村さんらが海外に行って火傷をする様子が放映されましたが、
日本のスタジオで行っていたら、放送事故だと思います。
もし泡に触れるのであれば、十分時間を置いてから、演示者が触れるだけにとどめるべきです。
十分時間を置いたものでも、泡に触れた指に刺激を感じることがあります。
ヨウ化カリウムが上手く混じっていない部分があって、分解されていない可能性もあります(未検証)。
■液体窒素
液体窒素の取り扱いや窒息の認識が誤っているものがあります。
液体窒素を水やお湯に入れると、液体窒素が急激に沸騰し、白い煙(湯気)が大量に発生します。
この白い煙の正体は、空気中に含まれる水蒸気が液体の水に戻ったものです。
つまり窒素だけではなく、空気が混じっているので、吸っても大丈夫だと言う方がいらっしゃいます。
しかし、酸素濃度が18%を切った気体を一吸いするだけで、窒息する場合があり、酷いと意識を失います。
通常の空気の酸素濃度は21%ですので、たった3%が窒素に置き換わっただけで危険性があるのです。
観客の方が深く呼吸をした場合は特に危険ですので、吸わせることは避けた方が良いと思います。
液体窒素で凍らせた食材を食べ、胃が破裂した例もあります。
ただでさえ凍傷の危険性があり、食材は何でもよい訳ではありません。
マシュマロを液体窒素に入れて食べるのは多く行われていますが、投入時間などを考えないと危険です。
弊社ではお子様に食べさせる行為は一切行っておりません。
危険な行為が目に余るので、記載させて頂きました。
出演動画がUPされました!
2016年12月09日
J:COMチャンネル「いちごくらぶアドベンチャー」の出演回の動画が、ようやくYouTubeにアップされました。
https://youtu.be/yz3SKADd6tE
諸事情でこの回をもって、いちごくらぶアドベンチャーは休止しているそう。
どうやらYouTubeにあげるのを忘れられていたようですw
大変お待たせ致しました。
最後の方で「どうしてシャボン玉はふわふわ浮くの?」という、保育園児の素朴な疑問にお答えしています。
えっ?軽いから?
いえいえ、そんな答えでは納得できませんよ。
えっ?当たり前だろって?
当たり前のことを当たり前ととらえないことが、科学では重要だと思いますよ。
と言いつつ、依頼を受けたときにはその率直すぎる疑問に、私「かず先生」も一瞬戸惑いが。
さすが、子どもたちの発想は素直で豊か。
子どもたちに負けていられない!と、実験を交え工夫して解説しましたよ~。
https://youtu.be/yz3SKADd6tE
諸事情でこの回をもって、いちごくらぶアドベンチャーは休止しているそう。
どうやらYouTubeにあげるのを忘れられていたようですw
大変お待たせ致しました。
最後の方で「どうしてシャボン玉はふわふわ浮くの?」という、保育園児の素朴な疑問にお答えしています。
えっ?軽いから?
いえいえ、そんな答えでは納得できませんよ。
えっ?当たり前だろって?
当たり前のことを当たり前ととらえないことが、科学では重要だと思いますよ。
と言いつつ、依頼を受けたときにはその率直すぎる疑問に、私「かず先生」も一瞬戸惑いが。
さすが、子どもたちの発想は素直で豊か。
子どもたちに負けていられない!と、実験を交え工夫して解説しましたよ~。
ホタルを見てきました。
2015年06月08日
先日の土曜日、子ども達を引き連れてホタルを見に行ってきました。
熊本市は割りと近くでもホタルが見られる場所が多く、自然の豊かさを感じます。
私が知っている穴場では、ホタルの数は少な目ですが、人が少なくゆっくりと見られます。
人が増えると困るので、場所は公開しませんwww
今回見られたのはゲンジボタル。
ヘケボタル・ヒメボタルに比べ身体が大きく、ゆったりと光るのが特徴で、私はこちらの方が大好きです。
今年のピークは早かったようで、数は少なかったですね。
さて、「メスは光らない」と思っている方も多いようですが、光りますよ!
メスはあまり動かず、草や葉に止まって弱い光を出しています。
オスは飛び回って強い光をだし、メスを見つけるとスッと寄っていきます。
とても美しい求愛行動ですね。
ちなみに、ホタルの光はプロポーズの光が有名ですが、他にも敵を威嚇するための光などもありますよ。
卵や、幼虫、蛹も、生涯を通して光るんです。
せっかくなら、近くでも観察してみたいですよね。
こっちの水は甘いぞ…という歌がありますが、水ではなくもっと確実なホタルの呼び寄せ方があります。
ペンライトのようなもので、メスと同じようなタイミングで点滅させるんですよ。
ただし、あまり強い光は見ている人にも、ホタルにも迷惑ですので、弱い光でやってみてくださいね。
ちなみに、当教室のオリジナル実験「ホタルスライム」は、
本物のホタルと同じ「ルシフェリン-ルシフェラーゼ発光」のスライムです。
同じく、幻想的な光を見ることができる、美しい実験です。
熊本市は割りと近くでもホタルが見られる場所が多く、自然の豊かさを感じます。
私が知っている穴場では、ホタルの数は少な目ですが、人が少なくゆっくりと見られます。
人が増えると困るので、場所は公開しませんwww
今回見られたのはゲンジボタル。
ヘケボタル・ヒメボタルに比べ身体が大きく、ゆったりと光るのが特徴で、私はこちらの方が大好きです。
今年のピークは早かったようで、数は少なかったですね。
さて、「メスは光らない」と思っている方も多いようですが、光りますよ!
メスはあまり動かず、草や葉に止まって弱い光を出しています。
オスは飛び回って強い光をだし、メスを見つけるとスッと寄っていきます。
とても美しい求愛行動ですね。
ちなみに、ホタルの光はプロポーズの光が有名ですが、他にも敵を威嚇するための光などもありますよ。
卵や、幼虫、蛹も、生涯を通して光るんです。
せっかくなら、近くでも観察してみたいですよね。
こっちの水は甘いぞ…という歌がありますが、水ではなくもっと確実なホタルの呼び寄せ方があります。
ペンライトのようなもので、メスと同じようなタイミングで点滅させるんですよ。
ただし、あまり強い光は見ている人にも、ホタルにも迷惑ですので、弱い光でやってみてくださいね。
ちなみに、当教室のオリジナル実験「ホタルスライム」は、
本物のホタルと同じ「ルシフェリン-ルシフェラーゼ発光」のスライムです。
同じく、幻想的な光を見ることができる、美しい実験です。
過保護・潔癖の罪。
2012年11月25日
子どもたちが外で裸足で遊ぶ事をどう思いますか?
手を洗わない事をどう思いますか?
消毒する事をどう思いますか?
無菌状態にできれば一番いいのに。
そのような考え方を持っている方は、見方を変える必要があると思います。
特に小さな頃は、病気に対する抵抗力が弱く、すぐ病気になるものです。
だからと言って、過剰なまでに潔癖になるのは子どもたちの将来にとって良いものではありません。
子どもの頃から、ある一定の不潔を経験することで、抵抗力をつけることができるのです。
細菌は肉眼では見えませんが、貴方の手にも口の中にもお腹の中にも数え切れないほどの細菌が住んでいます。
腸内にはいわゆる善玉菌がいてはじめて正常な腸の活動が行なわれます。
「細菌=悪い」というイメージは捨ててください。
空気中にもカビの胞子やウイルス、細菌が飛んでいます。
これだけの細菌やカビ、ウイルスにさらされていても毎日のようには病気になりませんよね?
これは体に防御する機能があるからです。
無菌状態というのはこの防御する機能が必要なくなり、機能低下を引き起こします。
極端な過保護、潔癖は、健康に悪影響を及ぼします。
自然とふれあい、普通に過ごすことが子どもたちにとって最適なのですね。
ただし、喘息やハウスダスト等へのアレルギーを発症している場合はアレルゲンへの接触は控えるべきです。
手を洗わない事をどう思いますか?
消毒する事をどう思いますか?
無菌状態にできれば一番いいのに。
そのような考え方を持っている方は、見方を変える必要があると思います。
特に小さな頃は、病気に対する抵抗力が弱く、すぐ病気になるものです。
だからと言って、過剰なまでに潔癖になるのは子どもたちの将来にとって良いものではありません。
子どもの頃から、ある一定の不潔を経験することで、抵抗力をつけることができるのです。
細菌は肉眼では見えませんが、貴方の手にも口の中にもお腹の中にも数え切れないほどの細菌が住んでいます。
腸内にはいわゆる善玉菌がいてはじめて正常な腸の活動が行なわれます。
「細菌=悪い」というイメージは捨ててください。
空気中にもカビの胞子やウイルス、細菌が飛んでいます。
これだけの細菌やカビ、ウイルスにさらされていても毎日のようには病気になりませんよね?
これは体に防御する機能があるからです。
無菌状態というのはこの防御する機能が必要なくなり、機能低下を引き起こします。
極端な過保護、潔癖は、健康に悪影響を及ぼします。
自然とふれあい、普通に過ごすことが子どもたちにとって最適なのですね。
ただし、喘息やハウスダスト等へのアレルギーを発症している場合はアレルゲンへの接触は控えるべきです。
無重力は存在しない?
2012年11月21日
星出さんお帰りなさい!
星出さんが4ヶ月余りに及ぶ、国際宇宙ステーションの長期滞在から帰還されました。
で、ちょっとした宇宙の話。
一般的に「宇宙=無重力」というイメージを持つと思います。
ですが、正確に言えば無重力という場所は存在しません。
国際宇宙ステーションに居ようが、地球の重力の影響を受けます。
もっと離れた月だって、地球の重力があるから周回しているのですから。
地球の重力の影響を受けているはずなのに、
国際宇宙ステーションからの映像を見ると、皆プカプカ浮かんでいますよね?
これは常に地球に落ちているからです。
常に重力に対する支えがない状態が作られると、重力を体感できない、つまり無重力状態になります。
では、国債宇宙ステーションをはじめ、地球を周回している衛生はなぜ落ちてこないのでしょうか?
それは、落ちながら水平方向に高速で移動しているからです。
落ちたとしても水平方向にすすめば、地球から離れることができます。
これを繰り返して常に落ちている状態を作り出すのです。
宇宙は星で満ちています。
つまり、どこにだって重力が存在するのですね。
「宇宙は無重力」という当たり前だと思われる事象も、実は簡単にそうだとは言えない。
このような常識が、科学を思考する上で邪魔になることが多々あるのです。
星出さんが4ヶ月余りに及ぶ、国際宇宙ステーションの長期滞在から帰還されました。
で、ちょっとした宇宙の話。
一般的に「宇宙=無重力」というイメージを持つと思います。
ですが、正確に言えば無重力という場所は存在しません。
国際宇宙ステーションに居ようが、地球の重力の影響を受けます。
もっと離れた月だって、地球の重力があるから周回しているのですから。
地球の重力の影響を受けているはずなのに、
国際宇宙ステーションからの映像を見ると、皆プカプカ浮かんでいますよね?
これは常に地球に落ちているからです。
常に重力に対する支えがない状態が作られると、重力を体感できない、つまり無重力状態になります。
では、国債宇宙ステーションをはじめ、地球を周回している衛生はなぜ落ちてこないのでしょうか?
それは、落ちながら水平方向に高速で移動しているからです。
落ちたとしても水平方向にすすめば、地球から離れることができます。
これを繰り返して常に落ちている状態を作り出すのです。
宇宙は星で満ちています。
つまり、どこにだって重力が存在するのですね。
「宇宙は無重力」という当たり前だと思われる事象も、実は簡単にそうだとは言えない。
このような常識が、科学を思考する上で邪魔になることが多々あるのです。
不老不死の科学。
2012年11月19日
大昔から、多くの者が望んできた不老不死。
実現してしまったら、不老不死の本人は苦しむ結果になるのかもしれませんが、
「寿命」というものは科学的に解明されつつあります。
さて、ベニクラゲというクラゲがいます。
「不老」ではありませんが「不死」とは呼べるかもしれません。
一度、老化を辿りますが、死ぬ寸前に若返り始め、生まれた頃にリセットされる驚きの生物です。
もちろん、物理的に殺してしまえば死んでしまうので、完全なる不死ではありません。
私は遺伝子工学が専門ですが、この系統の人間なら寿命を決めるものは誰でも知っています。
「テロメア」と呼ばれる、染色体(DNA)の両端の部位です。
若い細胞というのは細胞分裂を盛んに行ない、新しい細胞を生み出します。
ところが、細胞分裂はどれだけでも起きる訳ではなく、限度回数があります。
この限度回数を決めているのが「テロメア」だろうと言われています。
細胞分裂を繰り返す度に、テロメアという部位は短くなっていきます。
テロメアがなくなってしまった細胞は、それ以上分裂することがなくなります。
こうなると、その細胞自身の寿命までで終わり。
あとは死に向かうしかありません。
細胞死が増えれば、体中の器官は不調をきたし、生命を維持できなくなります。
ということは、テロメアをどうにか伸ばすことができれば、細胞分裂を復活させられ、生命を維持することができるようになります。
「テロメアの長さを維持すること」が不老不死につながるのです。
といっても、体中の全ての細胞のテロメアを伸ばさなければなりませんから、簡単な話ではありません。
体が1つの細胞からなる、単細胞生物であればとても簡単なのですが。
私でも遺伝子操作して伸ばせます(笑)
ところで、活性酸素が老化につながる話を聞いたことがあるでしょうか。
活性酸素はテロメアの短縮を早めるのではないかと言われています。
だから老化が早まるのですね。
ベニクラゲは、若返りを行ない出だすと、このテロメアも長くなります。
命の巻き戻しを行なう、大変特殊な生物ですね。
実現してしまったら、不老不死の本人は苦しむ結果になるのかもしれませんが、
「寿命」というものは科学的に解明されつつあります。
さて、ベニクラゲというクラゲがいます。
「不老」ではありませんが「不死」とは呼べるかもしれません。
一度、老化を辿りますが、死ぬ寸前に若返り始め、生まれた頃にリセットされる驚きの生物です。
もちろん、物理的に殺してしまえば死んでしまうので、完全なる不死ではありません。
私は遺伝子工学が専門ですが、この系統の人間なら寿命を決めるものは誰でも知っています。
「テロメア」と呼ばれる、染色体(DNA)の両端の部位です。
若い細胞というのは細胞分裂を盛んに行ない、新しい細胞を生み出します。
ところが、細胞分裂はどれだけでも起きる訳ではなく、限度回数があります。
この限度回数を決めているのが「テロメア」だろうと言われています。
細胞分裂を繰り返す度に、テロメアという部位は短くなっていきます。
テロメアがなくなってしまった細胞は、それ以上分裂することがなくなります。
こうなると、その細胞自身の寿命までで終わり。
あとは死に向かうしかありません。
細胞死が増えれば、体中の器官は不調をきたし、生命を維持できなくなります。
ということは、テロメアをどうにか伸ばすことができれば、細胞分裂を復活させられ、生命を維持することができるようになります。
「テロメアの長さを維持すること」が不老不死につながるのです。
といっても、体中の全ての細胞のテロメアを伸ばさなければなりませんから、簡単な話ではありません。
体が1つの細胞からなる、単細胞生物であればとても簡単なのですが。
私でも遺伝子操作して伸ばせます(笑)
ところで、活性酸素が老化につながる話を聞いたことがあるでしょうか。
活性酸素はテロメアの短縮を早めるのではないかと言われています。
だから老化が早まるのですね。
ベニクラゲは、若返りを行ない出だすと、このテロメアも長くなります。
命の巻き戻しを行なう、大変特殊な生物ですね。
落葉する理由。
2012年11月19日
この時期のけやき通りは落ち葉とのイタチごっこ。
毎朝、必死に落ち葉を掃く会社員の方を見ます。
ご苦労様です。
さて、なぜ落葉樹は冬になると葉を落とすのでしょう?
これは省エネと関係があります。
葉は食べることができない植物にとって重要なものです。
光を浴びることで光合成を行い、生命活動に必要な養分(デンプン)を作るのです。
光合成には他に水を必要とします。
葉の表皮にある気孔とよばれる穴から水を蒸発することで根から吸い上げる力を生み出します。
ストローのような感じですね。
葉で作られた養分は師管という管を通って全身に運ばれ、新しい枝葉を作るエネルギーとして使われます。
日差しが強い時期は十分な養分が得られるのでこれを繰り返せば良いのですが、
冬になると日差しは弱く、気温も低くなるため、光合成の効率が落ちてしまいます。
そこで落葉樹はエネルギーを作っては使うというサイクルをストップさせます。
葉を落とせば水の循環量が少なくなります。
新しい枝葉を作らないことでエネルギーの消費も抑えられます。
動物で言えば冬眠の始まりが「落葉」なのですね。
もう一つの理由として、自ら肥料を作り出そうとしているという見方もあります。
葉を根元に落とし、バクテリアに分解してもらって肥料を得るのです。
これは落葉樹に限りません。
常緑樹も古い葉は落とします。
よく掃除で、葉の根元まできれいサッパリ掃いてしまう人がいますが、本来植物にとっては良いことではありません。
動物も植物も、生命活動の危機となり得る越冬方法を工夫しているのです。
私たち人間はより住みやすい環境を求めるばかりに、エネルギーを使いまくりますが、
ここに来てようやく省エネにたどり着きました。
消費することと温存することの両方のバランスを上手く取ることが自然な姿なのですね。
毎朝、必死に落ち葉を掃く会社員の方を見ます。
ご苦労様です。
さて、なぜ落葉樹は冬になると葉を落とすのでしょう?
これは省エネと関係があります。
葉は食べることができない植物にとって重要なものです。
光を浴びることで光合成を行い、生命活動に必要な養分(デンプン)を作るのです。
光合成には他に水を必要とします。
葉の表皮にある気孔とよばれる穴から水を蒸発することで根から吸い上げる力を生み出します。
ストローのような感じですね。
葉で作られた養分は師管という管を通って全身に運ばれ、新しい枝葉を作るエネルギーとして使われます。
日差しが強い時期は十分な養分が得られるのでこれを繰り返せば良いのですが、
冬になると日差しは弱く、気温も低くなるため、光合成の効率が落ちてしまいます。
そこで落葉樹はエネルギーを作っては使うというサイクルをストップさせます。
葉を落とせば水の循環量が少なくなります。
新しい枝葉を作らないことでエネルギーの消費も抑えられます。
動物で言えば冬眠の始まりが「落葉」なのですね。
もう一つの理由として、自ら肥料を作り出そうとしているという見方もあります。
葉を根元に落とし、バクテリアに分解してもらって肥料を得るのです。
これは落葉樹に限りません。
常緑樹も古い葉は落とします。
よく掃除で、葉の根元まできれいサッパリ掃いてしまう人がいますが、本来植物にとっては良いことではありません。
動物も植物も、生命活動の危機となり得る越冬方法を工夫しているのです。
私たち人間はより住みやすい環境を求めるばかりに、エネルギーを使いまくりますが、
ここに来てようやく省エネにたどり着きました。
消費することと温存することの両方のバランスを上手く取ることが自然な姿なのですね。
雲はなぜ落ちてこないのか?
2012年11月16日
いえ、落ちて来ることもありますよww
落ちてきたのが雨であり雪であり雹霰です。
ある中学生に質問されたことです。
「当たり前の事を当たり前のこととして捉えない」というものの見方は、科学にとってとても大切なことです。
雲はの正体は霧と同じ水の細かな粒です。
空気中に向かってスプレーや霧吹きをして、フーッと吹けば、簡単に舞い上がりますよね?
同じことです。
雲は上昇気流によって生まれます。
つまり、風が上に舞っている訳ですから、小さな水の粒は落ちることができません。
仮に、急に下降気流になったとしても、地表に近づくほど気圧が高くなり、空気の温度も高くなります。
こうなると雲は消えていきます。
高気圧では下降気流、低気圧では上昇気流ができます。
そのため、低気圧の場合は大抵天気が悪いのです。
雲の量が多くなると、水の粒同士がぶつかる確率が高くなります。
こうして水の粒が大きく成長し、上昇気流より雨にかかる重力の方が勝ったときに落ちてきます。
これが雨です。
同じように気温によっては雪や雹・霰が出来上がります。
落ちてきたのが雨であり雪であり雹霰です。
ある中学生に質問されたことです。
「当たり前の事を当たり前のこととして捉えない」というものの見方は、科学にとってとても大切なことです。
雲はの正体は霧と同じ水の細かな粒です。
空気中に向かってスプレーや霧吹きをして、フーッと吹けば、簡単に舞い上がりますよね?
同じことです。
雲は上昇気流によって生まれます。
つまり、風が上に舞っている訳ですから、小さな水の粒は落ちることができません。
仮に、急に下降気流になったとしても、地表に近づくほど気圧が高くなり、空気の温度も高くなります。
こうなると雲は消えていきます。
高気圧では下降気流、低気圧では上昇気流ができます。
そのため、低気圧の場合は大抵天気が悪いのです。
雲の量が多くなると、水の粒同士がぶつかる確率が高くなります。
こうして水の粒が大きく成長し、上昇気流より雨にかかる重力の方が勝ったときに落ちてきます。
これが雨です。
同じように気温によっては雪や雹・霰が出来上がります。
錬金術は可能です♪
2012年11月14日
【錬金術】ありふれた物質から金を生み出して金儲けをしようとすること
中世ヨーロッパにおいて、錬金術というのが流行りました。
安い物質が高い金に変われば儲けもんですから。
錬金術を行なう人を錬金術師と言います。
錬金術師達は金を作ろうと試みる過程から、様々な化学反応を発見しました。
錬金術の事をアルケミー(alchemy)、錬金術師の事をアルケミスト(alchemist)と呼びます。
現代の「化学」は英語でケミストリー(chemistry)と言います。
つまり、「化学」語源は「錬金術」なのですね。
そう、「錬金術」が変化して「化学」という学問ができたのです。
人間の悪い意味での欲が、現在は人のためになる技術として変化を遂げたんですね。
でも、その欲があるからこそ、化学はここまで発展できたのでしょうね。
さて、現代の科学では理論上、錬金術は可能です。
詳しい話は別の記事でご紹介するとして…。
しかし、実現するには凄まじいエネルギーが必要です。
つまり錬金術を行なうには、同じ質量の金を買う以上のお金が必要なんです。
これでは本末転倒ですな

中世ヨーロッパにおいて、錬金術というのが流行りました。
安い物質が高い金に変われば儲けもんですから。
錬金術を行なう人を錬金術師と言います。
錬金術師達は金を作ろうと試みる過程から、様々な化学反応を発見しました。
錬金術の事をアルケミー(alchemy)、錬金術師の事をアルケミスト(alchemist)と呼びます。
現代の「化学」は英語でケミストリー(chemistry)と言います。
つまり、「化学」語源は「錬金術」なのですね。
そう、「錬金術」が変化して「化学」という学問ができたのです。
人間の悪い意味での欲が、現在は人のためになる技術として変化を遂げたんですね。
でも、その欲があるからこそ、化学はここまで発展できたのでしょうね。
さて、現代の科学では理論上、錬金術は可能です。
詳しい話は別の記事でご紹介するとして…。
しかし、実現するには凄まじいエネルギーが必要です。
つまり錬金術を行なうには、同じ質量の金を買う以上のお金が必要なんです。
これでは本末転倒ですな

鼻くそを食べる理由(爆)
2012年11月09日
なんか、銀杏がうんこ臭い理由の記事が割りと人気があるので…
思い出したのでついでに、鼻くそを食べる理由を科学してみたいと思います
鼻くそを食べている人を見たことがない人はいないのではないでしょうか?
特に子どもたちの多くが鼻をほじり、口にパクッと
そして、親に注意される光景って、珍しくありません。
きっと、大人も見えないところで鼻くそを食べている人って、多いと思いますよwww
ここまで多くの人が鼻くそを汚いと知りながら食べてしまうのなら、本能的な行動と言えるでしょう。
何か科学的意味があるに違いありません。
実はこのことについてある医師が論文を出しています。
これが正しいかどうかは分かりませんよ。
でも、私はこの説に賛成です。
空気中に漂うホコリや細菌、ウイルス、花粉、胞子などは、鼻毛や鼻の粘膜に引っかかります。
できるだけクリーンな空気を肺に入れるためです。
これらが鼻水などと共に固まったものが鼻くそです。
実はこれを口から体内に入れることで、細菌・ウイルス・花粉などに対する抗体を作るのではないかといわれています。
つまり、予防接種のようなものです。
不衛生この上ない行動に見えますが、理にかなっています。
消化器系に比べ、肺は細菌やウイルスに弱く、肺炎などの重病を引き起こすこともあります。
ですから、鼻がフィルターになっているわけです。
ところが、このような汚いものを飲み込んでも、まず第一に通る胃でほとんどが殺菌されます。
胃酸の主成分は「塩酸」だからです。
小中学校でも扱う金属が溶けるあれです。
塩酸はタンパク質を溶かしますから、胃酸にさらされた細菌やウイルスは、大抵死滅してしまいます。
細菌の中には、腸内で活躍してくれる良い細菌(一般に善玉菌と言いますね)もいます。
これらの中の一部が腸まで届けば、腸内環境を良くしてくれる可能性もあります。
人間だけではありません。
チンパンジーやゴリラなどが鼻をほじり、口に運ぶ映像を見ることがあります。
共通する本能だと言えるでしょう。
まぁ、社会的には鼻くそ摂取を推進できませんが
隠れてこっそりはアリ、なのかもしれません

思い出したのでついでに、鼻くそを食べる理由を科学してみたいと思います

鼻くそを食べている人を見たことがない人はいないのではないでしょうか?
特に子どもたちの多くが鼻をほじり、口にパクッと

そして、親に注意される光景って、珍しくありません。
きっと、大人も見えないところで鼻くそを食べている人って、多いと思いますよwww
ここまで多くの人が鼻くそを汚いと知りながら食べてしまうのなら、本能的な行動と言えるでしょう。
何か科学的意味があるに違いありません。
実はこのことについてある医師が論文を出しています。
これが正しいかどうかは分かりませんよ。
でも、私はこの説に賛成です。
空気中に漂うホコリや細菌、ウイルス、花粉、胞子などは、鼻毛や鼻の粘膜に引っかかります。
できるだけクリーンな空気を肺に入れるためです。
これらが鼻水などと共に固まったものが鼻くそです。
実はこれを口から体内に入れることで、細菌・ウイルス・花粉などに対する抗体を作るのではないかといわれています。
つまり、予防接種のようなものです。
不衛生この上ない行動に見えますが、理にかなっています。
消化器系に比べ、肺は細菌やウイルスに弱く、肺炎などの重病を引き起こすこともあります。
ですから、鼻がフィルターになっているわけです。
ところが、このような汚いものを飲み込んでも、まず第一に通る胃でほとんどが殺菌されます。
胃酸の主成分は「塩酸」だからです。
小中学校でも扱う金属が溶けるあれです。
塩酸はタンパク質を溶かしますから、胃酸にさらされた細菌やウイルスは、大抵死滅してしまいます。
細菌の中には、腸内で活躍してくれる良い細菌(一般に善玉菌と言いますね)もいます。
これらの中の一部が腸まで届けば、腸内環境を良くしてくれる可能性もあります。
人間だけではありません。
チンパンジーやゴリラなどが鼻をほじり、口に運ぶ映像を見ることがあります。
共通する本能だと言えるでしょう。
まぁ、社会的には鼻くそ摂取を推進できませんが

隠れてこっそりはアリ、なのかもしれません

銀杏がうんこ臭い理由(笑)
2012年11月08日
いやはや、美しい!
昨日リンクシェアしていただいたおてもやんブログのオフィシャルfacebookページに、今日は熊本県庁の銀杏並木の写真が。
しかし、私の頭に同時に出てきたのは、独特のうんこにも似た不快臭であります(^^;)
何と低脳な私の頭…。
ついでなので、うんこ臭い理由のお話を科学的にしてみますwww
銀杏の実には低脂肪酸が多く含まれています。
低脂肪酸の分解が進むと(つまり腐ると)、「酪酸(らくさん)」という臭い酸が発生します。
これは、バターやチーズにも含まれています。
バターから得られるので酪農の"酪"の字が付きました。
実は、哺乳類の大腸などでも発酵の結果、酪酸が発生します。
つまり、本物のうんこの臭いも酪酸の臭いが含まれているのであり、銀杏臭の原因と同じなのです。
足の裏臭も同じだそうです。
ではなぜイチョウは腐るとうんこ臭のする実を作るのでしょう?
たぶん仮説になるのではないかと思いますが、
この臭いを嫌う哺乳類に食べられないようにするためではないかと言われています。
実は哺乳類の鼻は酪酸に敏感にできています。
たぶんですが、排泄物を認識するためではないかと思います。
私たちはイチョウに「どうだ臭いだろ!あっち行け!」と言われているわけですね(笑)
最初に食べた人は何と勇気のある人でしょう。
植物は動けない代わりにこのような物質を上手く使って、花や実に誘引したり、逆に忌避したりして、子孫を残そうとしているのです。
ちなみに、唐辛子が辛いのも同じです。
哺乳類は辛く感じますが、鳥類は辛味を感じません。
鳥に食べてもらい、離れた場所で糞と一緒に種が出てくることで、広い範囲または違った環境に子孫を残そうとしているのです。
せっかく美しい写真を見ての、このお話。申し訳ありませぬ。
昨日リンクシェアしていただいたおてもやんブログのオフィシャルfacebookページに、今日は熊本県庁の銀杏並木の写真が。
しかし、私の頭に同時に出てきたのは、独特のうんこにも似た不快臭であります(^^;)
何と低脳な私の頭…。
ついでなので、うんこ臭い理由のお話を科学的にしてみますwww
銀杏の実には低脂肪酸が多く含まれています。
低脂肪酸の分解が進むと(つまり腐ると)、「酪酸(らくさん)」という臭い酸が発生します。
これは、バターやチーズにも含まれています。
バターから得られるので酪農の"酪"の字が付きました。
実は、哺乳類の大腸などでも発酵の結果、酪酸が発生します。
つまり、本物のうんこの臭いも酪酸の臭いが含まれているのであり、銀杏臭の原因と同じなのです。
足の裏臭も同じだそうです。
ではなぜイチョウは腐るとうんこ臭のする実を作るのでしょう?
たぶん仮説になるのではないかと思いますが、
この臭いを嫌う哺乳類に食べられないようにするためではないかと言われています。
実は哺乳類の鼻は酪酸に敏感にできています。
たぶんですが、排泄物を認識するためではないかと思います。
私たちはイチョウに「どうだ臭いだろ!あっち行け!」と言われているわけですね(笑)
最初に食べた人は何と勇気のある人でしょう。
植物は動けない代わりにこのような物質を上手く使って、花や実に誘引したり、逆に忌避したりして、子孫を残そうとしているのです。
ちなみに、唐辛子が辛いのも同じです。
哺乳類は辛く感じますが、鳥類は辛味を感じません。
鳥に食べてもらい、離れた場所で糞と一緒に種が出てくることで、広い範囲または違った環境に子孫を残そうとしているのです。
せっかく美しい写真を見ての、このお話。申し訳ありませぬ。