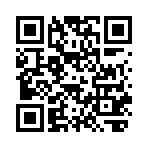スポンサーサイト
市科学展「金賞」、県展「優賞」おめでとう!
2014年11月25日
当教室の受講生が、夏休み自由研究で
熊本市科学展で「金賞」、熊本県科学展で「優賞」を取りました!
この場を借りてご報告致します。
また、他の受講生も市町村の科学展へ出展されております。
確かに、自由研究の実験方法について相談を受け、アドバイスしましたので、お礼の声をいただきましたが、
いえいえ…これは明らかにご本人様の力です!
出展作品を見てきましたが、たくさんの実験を自分で工夫して行っています。
私が協力できた部分は賞とは何も関係がありません。
模造紙にびっしりと書かれた文字にも驚きましたが、展示されていたノートに驚きました。
自由研究の記録が、ノートほとんど丸一冊分。
これは大学の研究並ですね!
来年こそは県の特別賞を狙って、がんばってくださいね!
熊本市科学展で「金賞」、熊本県科学展で「優賞」を取りました!
この場を借りてご報告致します。
また、他の受講生も市町村の科学展へ出展されております。
確かに、自由研究の実験方法について相談を受け、アドバイスしましたので、お礼の声をいただきましたが、
いえいえ…これは明らかにご本人様の力です!
出展作品を見てきましたが、たくさんの実験を自分で工夫して行っています。
私が協力できた部分は賞とは何も関係がありません。
模造紙にびっしりと書かれた文字にも驚きましたが、展示されていたノートに驚きました。
自由研究の記録が、ノートほとんど丸一冊分。
これは大学の研究並ですね!
来年こそは県の特別賞を狙って、がんばってくださいね!
勉強に適した照明☆
2012年11月23日
キャンプファイヤーや暖炉で静かに揺らぐ炎を見て、皆様はどのような感じを受けますか?
現代ではほとんどのお宅で暖炉はありませんし、焚き火も減りましたから、中々そのような場面が少ないかもしれませんね。
でも、なんとなく「落ち着く」とか「ボーッとしてくる」とか「寂しい感じがしてくる」という方が多いのではないでしょうか?
人間もその昔、野生で暮らしていたことがあります。
夜の炎は、当時の人間を寒さや猛獣から守りました。
その頃の記憶が、現代の人間にも残っています。
ですから、炎に似たオレンジの光には心を落ち着かせ、くつろがせる効果があります。
いわゆる「電球色」ですね。
このような色の照明は、リビングに最適です。
また、食卓でも食べ物をおいしそうに見せる効果がありますので、ダイニングにも最適です。
だから飲食店は大抵の場合、電球色なんです。
しかし、電球色は勉強には適していません。
勉強では頭をフル回転させなければなりませんから、日中の活発に活動する時間の光が最適です。
つまり、白い光の蛍光灯が最適なのです。
さて、前にリビングで勉強するのが良いというお話を書きましたが、リビングが電球職の場合は別途蛍光灯の電気スタンドをご準備される事をお勧めします。
目の健康にも明るい方が良いですし、もしオレンジの光の下で勉強をしている方は是非試してみてください。
現代ではほとんどのお宅で暖炉はありませんし、焚き火も減りましたから、中々そのような場面が少ないかもしれませんね。
でも、なんとなく「落ち着く」とか「ボーッとしてくる」とか「寂しい感じがしてくる」という方が多いのではないでしょうか?
人間もその昔、野生で暮らしていたことがあります。
夜の炎は、当時の人間を寒さや猛獣から守りました。
その頃の記憶が、現代の人間にも残っています。
ですから、炎に似たオレンジの光には心を落ち着かせ、くつろがせる効果があります。
いわゆる「電球色」ですね。
このような色の照明は、リビングに最適です。
また、食卓でも食べ物をおいしそうに見せる効果がありますので、ダイニングにも最適です。
だから飲食店は大抵の場合、電球色なんです。
しかし、電球色は勉強には適していません。
勉強では頭をフル回転させなければなりませんから、日中の活発に活動する時間の光が最適です。
つまり、白い光の蛍光灯が最適なのです。
さて、前にリビングで勉強するのが良いというお話を書きましたが、リビングが電球職の場合は別途蛍光灯の電気スタンドをご準備される事をお勧めします。
目の健康にも明るい方が良いですし、もしオレンジの光の下で勉強をしている方は是非試してみてください。
リビング勉強法
2012年11月16日
昨日、成績が良い子の特徴を「学校の授業がきちんと受け、その場で身についているかどうか」とお話しました。
家庭学習においての勉強法だけに着目をすると、そこにも大きな違いがある場合があります。
大変有名なことですが、「リビングで勉強するのが良い」ということです。
自分の部屋に閉じこもればゲームやまんがなどの誘惑が多くなります。
親の目が届く所でさせる方法が最も良いでしょう。
「雑音勉強法」をご紹介しましたが、静か過ぎるより適度な雑音があったほうが集中できます。
ですので、ご兄弟やご両親が生活している音が適度な雑音となり、勉強に最適です。
ただし、興味が引かれるテレビがついていたりやご兄弟がうるさい場合は適さないこともあります。
ご本人が全く興味を惹かれなさそうなテレビであればついていても問題ありません。
私自身も子どもの頃、勉強机は持っていましたが全く勉強した記憶はありません。
専ら、リビングです。
リビングで勉強していたころの成績はトップクラスでした。
うちの親はテレビを常につけているほうでしたので、勉強中もついていました。
消えたほうが落ち着かなくて勉強できなかった記憶があります。
高校生になって親も勉強を教えるのが辛くなり、
親の仕事が変わって、不在の時間が長くなり…。
その途端に成績が落ちたのは言うまでもありません
家庭学習においての勉強法だけに着目をすると、そこにも大きな違いがある場合があります。
大変有名なことですが、「リビングで勉強するのが良い」ということです。
自分の部屋に閉じこもればゲームやまんがなどの誘惑が多くなります。
親の目が届く所でさせる方法が最も良いでしょう。
「雑音勉強法」をご紹介しましたが、静か過ぎるより適度な雑音があったほうが集中できます。
ですので、ご兄弟やご両親が生活している音が適度な雑音となり、勉強に最適です。
ただし、興味が引かれるテレビがついていたりやご兄弟がうるさい場合は適さないこともあります。
ご本人が全く興味を惹かれなさそうなテレビであればついていても問題ありません。
私自身も子どもの頃、勉強机は持っていましたが全く勉強した記憶はありません。

専ら、リビングです。
リビングで勉強していたころの成績はトップクラスでした。
うちの親はテレビを常につけているほうでしたので、勉強中もついていました。
消えたほうが落ち着かなくて勉強できなかった記憶があります。
高校生になって親も勉強を教えるのが辛くなり、
親の仕事が変わって、不在の時間が長くなり…。
その途端に成績が落ちたのは言うまでもありません

成績良い子と何が違う?
2012年11月15日
成績が良い子と悪い子の違いは何でしょう?
この記事では、そういった観点から勉強法を考えてみたいと思います。
塾に通っていないからでしょうか?
通っている塾が良くないのでしょうか?
自宅での勉強が少ないからでしょうか?
単に能力が低いのでしょうか?
多くの場合、私は「いいえ」と答えます。
「学校の授業が、その場で身になるようにしっかり受けているかどうか」
これに尽きます。
成績が落ちだすと、今受けている授業が分からなくなります。
特に算数(数学)や英語は、新しい単元に移っても前の単元の知識を使うことが多いです。
特に英語は単語を覚えていなければ話になりません。
分からない授業は聞いても面白くないのは当然です。
常に頭の中が「?」でいっぱい。
そうして霧の中に迷い込んで行きます。
取り残した学習内容が増えると、「もう一体どこから手を付ければ良いか分からない」という状態に陥るのです。
学校の授業内容は、法律によって縛られていますから、
学習すべき内容は全て漏れなく教えられます。
これを全てその場で定着させることができれば、少なくとも公立受験は何も心配がいらなくなります。
チンプンカンプンなままに授業を受け、ボーッと過ごすのは大変時間が勿体無いです。
わざわざ受験勉強とか、試験勉強とかしなくても、真剣に取り組めば、家庭学習や塾の学習で苦労する事はなくなります。
さて、ほとんどの人は超人ではありませんから、授業を受けただけで全てを身につけられるわけではありませんね。
人は忘れる生き物ですが、繰り返し思い出すことで記憶を強固なものにできます。
そのために必要なのが宿題や復習、テストな訳です。
授業をしっかり受け、宿題をし、若干の復習(思い出し作業)をすること。
ごく当たり前の事を普通にこなすことが大切なのです。
さて、ここまで読んでくださっているという事は、
もしかするともう授業がチンプンカンプンになっている人の保護者様(あるいはご本人)かもしれませんね。
では、まず授業が分かる頃に戻してあげましょう。
どこから勉強を始めるのか、です。
【算数(数学)】
苦手分野が「割合」だろうが「分数」だろうが「体積」だろうが、
まずは基本の足し算・引き算・掛け算・割り算はできなければなりません。
そこをチェックしてください。
ミスが多い場合は計算ドリルなどで繰り返し練習しましょう。
次に、実際に苦手な分野でよく間違える問題を見ます。
原因を探ってください。
計算間違い?ならば、上記を実践していれば改善しているかもしれません。
原因がよく分からない場合は、教科書の単元の始めから読み直しながら、例題を解いていきましょう。
きっと、どこかで躓いているか、その単元の意義の理解がすすんでいないのです。
また「問題文が理解できていない」という場合も多いです。
まずは国語も勉強が必要かもしれません。
【国語】
漢字は覚えるしかありません。
アルファベットと違い、漢字には意味がたくさん含まれていますから、しっかり一字一字の意味を考えながら覚えましょう。
そのうち、知らない漢字に出会っても、なんとなく意味合いが理解できるようになるかもしれません。
さて、文章を読んで答えるような問題は厄介です。
問題は置いておいて、まずは文章を読みこなすこと。
そして、何を言わんとしているのか、きちんと理解していることが大切です。
漢字が分からないから意味が分からないのか、言い回しが難しいから分からないのか、作者の気持ちが読み取れないのか。
経験しかありません。
まずは、興味がある本から手をつけて、読書することをおすすめします。
【社会・理科】
他の教科に比べて、分かる授業を取り戻すのが楽な教科です。
なぜなら、新しい単元に移ると、前の単元の内容が分かっていなくても理解できる場合が多いからです。
理社の場合、新しい単元に移る際がポイントです。
「よし!ここからは真面目に授業を受けてやるぞ!」と、気合を入れてください。
復習として、別途苦手な単元を学習しましょう。
【英語】
中学生までであれば、単語さえ分かれば長文もほとんどの意味が分かると言われています。
まず英語が苦手な人は、単語を覚えることから始めましょう。
中学で習う必須英単語はリストにしてみると意外と少ないです。
日本語として使われているものが多く、大人なら発音が分かれば大体聞いたことがあるものばかりです。
聞いたことがある単語を削除すると、さらに少なくなります。
単語の覚え方はまた別の機会にお話します。
さて、文法は数学に似ています。
現在文を基本として確認。
特定の文法が分からないなら、その単元(文法)を始めから見直しましょう。
さて、読めば当たり前だと思われるかもしれませんが、とても大切なことです。
できるだけ分からないことが少ないうちに、克服しておくこと。
そして、今の授業に追いついたら、今後はきちんと授業を受けるように、宿題をするように頑張ることです。
塾や家庭教師は味付け程度でしかありませんよ。
この記事では、そういった観点から勉強法を考えてみたいと思います。
塾に通っていないからでしょうか?
通っている塾が良くないのでしょうか?
自宅での勉強が少ないからでしょうか?
単に能力が低いのでしょうか?
多くの場合、私は「いいえ」と答えます。
「学校の授業が、その場で身になるようにしっかり受けているかどうか」
これに尽きます。
成績が落ちだすと、今受けている授業が分からなくなります。
特に算数(数学)や英語は、新しい単元に移っても前の単元の知識を使うことが多いです。
特に英語は単語を覚えていなければ話になりません。
分からない授業は聞いても面白くないのは当然です。
常に頭の中が「?」でいっぱい。
そうして霧の中に迷い込んで行きます。
取り残した学習内容が増えると、「もう一体どこから手を付ければ良いか分からない」という状態に陥るのです。
学校の授業内容は、法律によって縛られていますから、
学習すべき内容は全て漏れなく教えられます。
これを全てその場で定着させることができれば、少なくとも公立受験は何も心配がいらなくなります。
チンプンカンプンなままに授業を受け、ボーッと過ごすのは大変時間が勿体無いです。
わざわざ受験勉強とか、試験勉強とかしなくても、真剣に取り組めば、家庭学習や塾の学習で苦労する事はなくなります。
さて、ほとんどの人は超人ではありませんから、授業を受けただけで全てを身につけられるわけではありませんね。
人は忘れる生き物ですが、繰り返し思い出すことで記憶を強固なものにできます。
そのために必要なのが宿題や復習、テストな訳です。
授業をしっかり受け、宿題をし、若干の復習(思い出し作業)をすること。
ごく当たり前の事を普通にこなすことが大切なのです。
さて、ここまで読んでくださっているという事は、
もしかするともう授業がチンプンカンプンになっている人の保護者様(あるいはご本人)かもしれませんね。
では、まず授業が分かる頃に戻してあげましょう。
どこから勉強を始めるのか、です。
【算数(数学)】
苦手分野が「割合」だろうが「分数」だろうが「体積」だろうが、
まずは基本の足し算・引き算・掛け算・割り算はできなければなりません。
そこをチェックしてください。
ミスが多い場合は計算ドリルなどで繰り返し練習しましょう。
次に、実際に苦手な分野でよく間違える問題を見ます。
原因を探ってください。
計算間違い?ならば、上記を実践していれば改善しているかもしれません。
原因がよく分からない場合は、教科書の単元の始めから読み直しながら、例題を解いていきましょう。
きっと、どこかで躓いているか、その単元の意義の理解がすすんでいないのです。
また「問題文が理解できていない」という場合も多いです。
まずは国語も勉強が必要かもしれません。
【国語】
漢字は覚えるしかありません。
アルファベットと違い、漢字には意味がたくさん含まれていますから、しっかり一字一字の意味を考えながら覚えましょう。
そのうち、知らない漢字に出会っても、なんとなく意味合いが理解できるようになるかもしれません。
さて、文章を読んで答えるような問題は厄介です。
問題は置いておいて、まずは文章を読みこなすこと。
そして、何を言わんとしているのか、きちんと理解していることが大切です。
漢字が分からないから意味が分からないのか、言い回しが難しいから分からないのか、作者の気持ちが読み取れないのか。
経験しかありません。
まずは、興味がある本から手をつけて、読書することをおすすめします。
【社会・理科】
他の教科に比べて、分かる授業を取り戻すのが楽な教科です。
なぜなら、新しい単元に移ると、前の単元の内容が分かっていなくても理解できる場合が多いからです。
理社の場合、新しい単元に移る際がポイントです。
「よし!ここからは真面目に授業を受けてやるぞ!」と、気合を入れてください。
復習として、別途苦手な単元を学習しましょう。
【英語】
中学生までであれば、単語さえ分かれば長文もほとんどの意味が分かると言われています。
まず英語が苦手な人は、単語を覚えることから始めましょう。
中学で習う必須英単語はリストにしてみると意外と少ないです。
日本語として使われているものが多く、大人なら発音が分かれば大体聞いたことがあるものばかりです。
聞いたことがある単語を削除すると、さらに少なくなります。
単語の覚え方はまた別の機会にお話します。
さて、文法は数学に似ています。
現在文を基本として確認。
特定の文法が分からないなら、その単元(文法)を始めから見直しましょう。
さて、読めば当たり前だと思われるかもしれませんが、とても大切なことです。
できるだけ分からないことが少ないうちに、克服しておくこと。
そして、今の授業に追いついたら、今後はきちんと授業を受けるように、宿題をするように頑張ることです。
塾や家庭教師は味付け程度でしかありませんよ。
雑音勉強法!?
2012年11月13日
シーンと静かな環境…
子どもに勉強をさせようという親御さんなら望む環境かもしれませんが、
静かな環境は集中力を欠くということをご存知でしょうか?
よく、ラジオや音楽、テレビがついていないと勉強できない、集中できないって人いますよね?
実は、あれは理にかなっているんです。
静かと言えば図書館でしょうか。
静か過ぎると、ちょっとした物音や話し声が気になってしまいます。
普段ならうるさいと思わない話し声でも、コソコソ聞こえると「うるさい」「邪魔だ」と感じてしまいませんか?
逆にカフェやファミレスなど、小さくBGMがかかっていたりザワザワしている所の方が、ある程度の人の話し声や物音には一々反応しなくなります。
ある企業は天井裏にスピーカーを設置し、空調機の駆動音のような雑音をわざわざ流しているそうです。
これによって、薄いパーテーションの向こうで行なわれている会議や、社員がたたくキーボードの音、咳払いなどが気にならなくなり、業務に集中できるというのです。
さて空調音は極端な例として、音楽を流すことについて考えてみます。
知っている音楽はどうしても頭の中でメロディーを追いかけ始めたりすることがありますから、決して良くはありません。
私が音楽の中で良いと感じたのはジャズです。
メロディーラインが分かりにくいジャズは、雑音的に聞き流すことができます。
雰囲気もいいですね。
ただ、ジャズをやっている人にとっては興味深々で聞いてしまうかもしれませんね。
私は音楽をやっていましたが、ジャンルが随分違うので、面白いとは感じますが、聞き流すことも可能でした。
吹奏楽部やピアノが弾ける人にもおすすめかもしれません。
音楽以外なら、全く興味のないラジオやテレビ番組を流しておくのも良いかもしれませんね。
場所が移動できる人ならカフェやファミレスなどで、勉強できる場所をを探してみるのもいいかもしれません。
「聞き流すことができる音」というのがポイントです。
ぜひ、お試しあれ

子どもに勉強をさせようという親御さんなら望む環境かもしれませんが、
静かな環境は集中力を欠くということをご存知でしょうか?
よく、ラジオや音楽、テレビがついていないと勉強できない、集中できないって人いますよね?
実は、あれは理にかなっているんです。
静かと言えば図書館でしょうか。
静か過ぎると、ちょっとした物音や話し声が気になってしまいます。
普段ならうるさいと思わない話し声でも、コソコソ聞こえると「うるさい」「邪魔だ」と感じてしまいませんか?
逆にカフェやファミレスなど、小さくBGMがかかっていたりザワザワしている所の方が、ある程度の人の話し声や物音には一々反応しなくなります。
ある企業は天井裏にスピーカーを設置し、空調機の駆動音のような雑音をわざわざ流しているそうです。
これによって、薄いパーテーションの向こうで行なわれている会議や、社員がたたくキーボードの音、咳払いなどが気にならなくなり、業務に集中できるというのです。
さて空調音は極端な例として、音楽を流すことについて考えてみます。
知っている音楽はどうしても頭の中でメロディーを追いかけ始めたりすることがありますから、決して良くはありません。
私が音楽の中で良いと感じたのはジャズです。
メロディーラインが分かりにくいジャズは、雑音的に聞き流すことができます。
雰囲気もいいですね。
ただ、ジャズをやっている人にとっては興味深々で聞いてしまうかもしれませんね。
私は音楽をやっていましたが、ジャンルが随分違うので、面白いとは感じますが、聞き流すことも可能でした。
吹奏楽部やピアノが弾ける人にもおすすめかもしれません。
音楽以外なら、全く興味のないラジオやテレビ番組を流しておくのも良いかもしれませんね。
場所が移動できる人ならカフェやファミレスなどで、勉強できる場所をを探してみるのもいいかもしれません。
「聞き流すことができる音」というのがポイントです。
ぜひ、お試しあれ

就職に有利な教育。
2012年11月12日
医師免許を取れば、医者になれます。
薬剤師免許をとれば、薬剤師になれます。
司法試験に通れば、弁護士や裁判官になれます。
このような最難関と言われる国家資格をとれば、ある程度の未来は約束されるかもしれません。
しかし今の世の中、厳しい現実が待ち受けています。
昔なら、一流大学を出れば、一流企業への就職が約束されていたのかもしれません。
しかし、一流大学を出ようが資格を取ろうが、未来を約束された人は皆無です。
どうにか自分で道を切り開いていかなければなりません。
私の企業に、ある怪文書が届きました
今の司法試験や司法制度に対する文句が長々と書き連ねてあります。
どうやら、司法試験に通らない言い訳がしたいようです。
で、とりあえず私が勤める企業で働きたいと。
最後に、「早稲田大学卒 ○○(名前)」と書かれています。
ハハ…
"早稲田大学卒"は肩書きではありませんよ…。
彼は一体何を学んできたのでしょうね
企業が欲している人材は、「学生時代の成績が良い者」ではありません。
企業を支えてくれる人材になってくれる候補者です。
成績が良いことと仕事ができる事は別問題。
他の社員や他企業ときちんとコミュニケーションができる人材か。
嫌な仕事・辛い仕事でも、やっていける人材か。
幅広いものの見方ができる人材か。
学校の授業だけでは学べないことばかりです。
勉学については参考程度として考えておいた方がいいでしょう。
面接に通らない人、書類選考で落ちる人。
もう一度客観的に自分を見てください。
他の人ではなく、自分を選んでもらえるだけの特別な価値をアピールしていますか?
ありがちなことばかりを書いていませんか?
単なる一流大学出よりも、学生時代からしっかりアルバイトをし、趣味を持ち、スポーツに取り組み…。
そうした人のほうが、魅力的で知性に溢れています。
事実、会社で「使える人」というのはそういう人です。
就職に有利な教育とは、勉学だけでなく、様々なことに取り組ませることだと思います。
薬剤師免許をとれば、薬剤師になれます。
司法試験に通れば、弁護士や裁判官になれます。
このような最難関と言われる国家資格をとれば、ある程度の未来は約束されるかもしれません。
しかし今の世の中、厳しい現実が待ち受けています。
昔なら、一流大学を出れば、一流企業への就職が約束されていたのかもしれません。
しかし、一流大学を出ようが資格を取ろうが、未来を約束された人は皆無です。
どうにか自分で道を切り開いていかなければなりません。
私の企業に、ある怪文書が届きました

今の司法試験や司法制度に対する文句が長々と書き連ねてあります。
どうやら、司法試験に通らない言い訳がしたいようです。
で、とりあえず私が勤める企業で働きたいと。
最後に、「早稲田大学卒 ○○(名前)」と書かれています。
ハハ…

"早稲田大学卒"は肩書きではありませんよ…。
彼は一体何を学んできたのでしょうね

企業が欲している人材は、「学生時代の成績が良い者」ではありません。
企業を支えてくれる人材になってくれる候補者です。
成績が良いことと仕事ができる事は別問題。
他の社員や他企業ときちんとコミュニケーションができる人材か。
嫌な仕事・辛い仕事でも、やっていける人材か。
幅広いものの見方ができる人材か。
学校の授業だけでは学べないことばかりです。
勉学については参考程度として考えておいた方がいいでしょう。
面接に通らない人、書類選考で落ちる人。
もう一度客観的に自分を見てください。
他の人ではなく、自分を選んでもらえるだけの特別な価値をアピールしていますか?
ありがちなことばかりを書いていませんか?
単なる一流大学出よりも、学生時代からしっかりアルバイトをし、趣味を持ち、スポーツに取り組み…。
そうした人のほうが、魅力的で知性に溢れています。
事実、会社で「使える人」というのはそういう人です。
就職に有利な教育とは、勉学だけでなく、様々なことに取り組ませることだと思います。
ほめてやらねば人は動かじ。
2012年11月10日
「やってみせ 言って聞かせて させてみて
ほめてやらねば 人は動かじ」
私が教育をする上で、絶対に忘れないようにしている名言です。
ご存知の方も多いでしょう。
山本五十六という太平洋戦争に関わった軍人の言葉です。
彼は軍人でありながら開戦前から、どうにか戦争を回避しよう、
開戦後は早く終わらせようとした人物です。
部下から非常に慕われていたそうです。
言葉には続きがあります。
「話し合い 耳を傾け 承認し
任せてやらねば 人は育たず
やっている 姿を感謝で見守って
信頼せねば 人は実らず」
ここで登場する「人」というのは、当然部下のことです。
上に立つものは、段々と勘違いをしやすいものです。
彼は上に立っても感謝を忘れなかったのですね。
人を広い心で受け止め、育て、敬う心。
尊敬されたはずですね
教育には必須の心だと思います。
ほめてやらねば 人は動かじ」
私が教育をする上で、絶対に忘れないようにしている名言です。
ご存知の方も多いでしょう。
山本五十六という太平洋戦争に関わった軍人の言葉です。
彼は軍人でありながら開戦前から、どうにか戦争を回避しよう、
開戦後は早く終わらせようとした人物です。
部下から非常に慕われていたそうです。
言葉には続きがあります。
「話し合い 耳を傾け 承認し
任せてやらねば 人は育たず
やっている 姿を感謝で見守って
信頼せねば 人は実らず」
ここで登場する「人」というのは、当然部下のことです。
上に立つものは、段々と勘違いをしやすいものです。
彼は上に立っても感謝を忘れなかったのですね。
人を広い心で受け止め、育て、敬う心。
尊敬されたはずですね

教育には必須の心だと思います。
正しい学習塾の選び方。
2012年11月09日
私は教員と学習塾の両方の経験があります。
私の観点から正しい塾選びをお教えします。
【ポイント1 形態を考える】
学習塾選びの大きな特徴である、形態を考えていきましょう。
[集団授業]
学校と同じように、講師主導で行なわれる集団授業の塾です。
○メリット
講師が育ちやすい環境にあり、安定感の有る授業が特徴です。
受験問題等に関して十分な研究が行なわれていますので、受験特有のテクニックが学べます。
高得点を狙いたい、既に成績が良い生徒におすすめです。
1対多なので、費用が安く抑えられます。
○デメリット
周りの生徒と同じ速さで授業が進みますので、付いていけなくなると無意味な授業になってしまいます。
講師の代えが効きませんので、合わない先生が担当になってしまっても文句が言えません。
1つ1つの質問への対応が難しくなります(授業時間外に質問を受け付けてくれる場所を提供している塾もあります)
[個別指導]
1対1で教えてくれる塾ですが、多くは1対3~5などです。
個別指導が完全1対1ではない事を知った方は驚かれますが、問題を解かせている時間などの時間は勿体無いので、その間に他の子の指導にまわります。ですから、家庭教師の無駄を省いたイメージです。
○メリット
授業速度や内容は個々人に応じた場合が多いので、その子に適した授業が可能になります。
成績が低い生徒は、集団塾よりも成績が伸びる可能性が高いです。
講師は大学生のアルバイトが多く、子どもたちと年齢が近いため通いやすいです。
○デメリット
大学生のアルバイト講師が教える場合が多く、集団塾に比べて解説や生徒指導の質が下がります。(ただし、受験を経験してから日が浅いので、生の経験談や受験テクニックを聞ける場合も多いです。)
講師と馴れ合いにならないよう注意が必要です。
人件費が高くつきますので、自ずと授業料が高くなります。
家庭教師よりは安く済みます。
[集団授業+個別指導]
両方のメリットを上手く取り入れた、複合型の授業を行なう塾もあります。
お近くにあれば一度体験してみてはいかがでしょうか。
【ポイント2 数字に騙されるな】
○○高校□名合格!という看板や広告に惑わされないようにしてください。
たった10人の生徒を大切に大切に扱う塾もあれば、うん千人の生徒を扱う塾まであります。
数を集め、できるだけ偏差値の高い高校を受けさせれば、合格者数は作ることができます。
「合格者が多い=成績が上がる塾、良い塾、行きたい高校に行かせてくれる塾」ではありません。
周囲の口コミにも耳を傾けてください。
【ポイント3 体験授業を受けよう】
多くの学習塾は無料または低額で体験授業を行なっています。
まずはテイスティング。
実際に行ってみて、子どもたちに合った塾を選びましょう。
【ポイント4 受験直前の費用を聞いておこう!】
多くの皆様がこれで失敗されています。
中学1~2年の授業料は安く抑えられていても、中3になった途端に授業料が跳ね上がる塾があります。
もちろん、中3の受験対策は時間も長くなるので高くはなりますが、法外な値段を請求する場合もありますので、入学当初から受験時の費用を聞いておきましょう。
せっかく慣れ親しんだ塾なのに、受験時期になって転塾って、けっこう聞く話です。
【ポイント5 入会金・教材費・設備費を聞いておこう!】
授業料が安くてホッとしている方!
ちゃんと他にかかる料金を把握していますか?
酷いところになると授業料は1万円台なのに、教材費が10万円近くなんてことも。
利益を別の所に乗せて、一見安く見せているところもありますから注意が必要です!
【ポイント6 転塾は素早く!】
学校の転校とは性質が違います。
通いだして良くないようだと思って転塾を決めたら素早く行ないましょう。
ズルズルと受験時期に差し掛かってしまうと、時間とお金が勿体無いです。
中には転塾費用を負担してくれる塾もありますから、まずは多くの塾を当たってみましょう。
ただし「成績が上がらない」という理由はちょっと待った!
【ポイント7 成績が上がらない!?】
退塾理由「成績が上がらないので」は、ちょっと待ったです!
まず、小学生~2年生週に1教科1回程度でしょう?
たったそれだけでは成績は上がらないはずです。
受験前の学年までは常に新しい学習を続けています。
毎日新しい分野に進んでいくのですから、基本は成績を維持することで精一杯なのです。
まず「成績を維持していることが素晴らしい」と考えてください。
そして重要なのは学力テストや模試などで、以前の学習内容をどれだけ定着させているか。
「成績が上がらない=塾が悪い」ではありません。
中には、成績が上がっているのに「上がらない」って言ってやめる方さえいらっしゃいます。
まず塾で使っているテキストやノートを覗いてみましょう。
しっかり学習していますか?
個別指導の場合、講師がしっかり指導しようと書き込みをしていますか?
実際に授業を見たことがありますか?見学できるようなら一度見学してみましょう。
確認できるものは広く確認してください。
その結果、「どうやら指導がいい加減な塾だ」とか「うちの子が集中できる環境の塾じゃないな」とかの判断ができれば、即転塾を考えましょう。
思いつくだけバラバラとお話しましたが、まだまだポイントはあるかもしれません。
続きはまた別の機会に。
私の観点から正しい塾選びをお教えします。
【ポイント1 形態を考える】
学習塾選びの大きな特徴である、形態を考えていきましょう。
[集団授業]
学校と同じように、講師主導で行なわれる集団授業の塾です。
○メリット
講師が育ちやすい環境にあり、安定感の有る授業が特徴です。
受験問題等に関して十分な研究が行なわれていますので、受験特有のテクニックが学べます。
高得点を狙いたい、既に成績が良い生徒におすすめです。
1対多なので、費用が安く抑えられます。
○デメリット
周りの生徒と同じ速さで授業が進みますので、付いていけなくなると無意味な授業になってしまいます。
講師の代えが効きませんので、合わない先生が担当になってしまっても文句が言えません。
1つ1つの質問への対応が難しくなります(授業時間外に質問を受け付けてくれる場所を提供している塾もあります)
[個別指導]
1対1で教えてくれる塾ですが、多くは1対3~5などです。
個別指導が完全1対1ではない事を知った方は驚かれますが、問題を解かせている時間などの時間は勿体無いので、その間に他の子の指導にまわります。ですから、家庭教師の無駄を省いたイメージです。
○メリット
授業速度や内容は個々人に応じた場合が多いので、その子に適した授業が可能になります。
成績が低い生徒は、集団塾よりも成績が伸びる可能性が高いです。
講師は大学生のアルバイトが多く、子どもたちと年齢が近いため通いやすいです。
○デメリット
大学生のアルバイト講師が教える場合が多く、集団塾に比べて解説や生徒指導の質が下がります。(ただし、受験を経験してから日が浅いので、生の経験談や受験テクニックを聞ける場合も多いです。)
講師と馴れ合いにならないよう注意が必要です。
人件費が高くつきますので、自ずと授業料が高くなります。
家庭教師よりは安く済みます。
[集団授業+個別指導]
両方のメリットを上手く取り入れた、複合型の授業を行なう塾もあります。
お近くにあれば一度体験してみてはいかがでしょうか。
【ポイント2 数字に騙されるな】
○○高校□名合格!という看板や広告に惑わされないようにしてください。
たった10人の生徒を大切に大切に扱う塾もあれば、うん千人の生徒を扱う塾まであります。
数を集め、できるだけ偏差値の高い高校を受けさせれば、合格者数は作ることができます。
「合格者が多い=成績が上がる塾、良い塾、行きたい高校に行かせてくれる塾」ではありません。
周囲の口コミにも耳を傾けてください。
【ポイント3 体験授業を受けよう】
多くの学習塾は無料または低額で体験授業を行なっています。
まずはテイスティング。
実際に行ってみて、子どもたちに合った塾を選びましょう。
【ポイント4 受験直前の費用を聞いておこう!】
多くの皆様がこれで失敗されています。
中学1~2年の授業料は安く抑えられていても、中3になった途端に授業料が跳ね上がる塾があります。
もちろん、中3の受験対策は時間も長くなるので高くはなりますが、法外な値段を請求する場合もありますので、入学当初から受験時の費用を聞いておきましょう。
せっかく慣れ親しんだ塾なのに、受験時期になって転塾って、けっこう聞く話です。
【ポイント5 入会金・教材費・設備費を聞いておこう!】
授業料が安くてホッとしている方!
ちゃんと他にかかる料金を把握していますか?
酷いところになると授業料は1万円台なのに、教材費が10万円近くなんてことも。
利益を別の所に乗せて、一見安く見せているところもありますから注意が必要です!
【ポイント6 転塾は素早く!】
学校の転校とは性質が違います。
通いだして良くないようだと思って転塾を決めたら素早く行ないましょう。
ズルズルと受験時期に差し掛かってしまうと、時間とお金が勿体無いです。
中には転塾費用を負担してくれる塾もありますから、まずは多くの塾を当たってみましょう。
ただし「成績が上がらない」という理由はちょっと待った!
【ポイント7 成績が上がらない!?】
退塾理由「成績が上がらないので」は、ちょっと待ったです!
まず、小学生~2年生週に1教科1回程度でしょう?
たったそれだけでは成績は上がらないはずです。
受験前の学年までは常に新しい学習を続けています。
毎日新しい分野に進んでいくのですから、基本は成績を維持することで精一杯なのです。
まず「成績を維持していることが素晴らしい」と考えてください。
そして重要なのは学力テストや模試などで、以前の学習内容をどれだけ定着させているか。
「成績が上がらない=塾が悪い」ではありません。
中には、成績が上がっているのに「上がらない」って言ってやめる方さえいらっしゃいます。
まず塾で使っているテキストやノートを覗いてみましょう。
しっかり学習していますか?
個別指導の場合、講師がしっかり指導しようと書き込みをしていますか?
実際に授業を見たことがありますか?見学できるようなら一度見学してみましょう。
確認できるものは広く確認してください。
その結果、「どうやら指導がいい加減な塾だ」とか「うちの子が集中できる環境の塾じゃないな」とかの判断ができれば、即転塾を考えましょう。
思いつくだけバラバラとお話しましたが、まだまだポイントはあるかもしれません。
続きはまた別の機会に。
塾の悪い癖。
2012年11月08日
良い学習塾に出会えた方は良いですが、こんな塾って結構多いです。
それは「学校(の先生)を批判する塾」です。
そんな塾にだけは絶対に行ってはいけません。
「そんなことも教えてもらってないの!?」
「学校の先生は公務員だから適当だね!」
マスコミを鵜呑みにして「学校はイジメにも対応してくれない。塾を信じろ。」
みたいな。
それはそれは、たくさん聞きますよ。
塾と学校の両方を経験した者として言います。
「学習塾こそ、世間知らず」です。
もちろんこれも、"全ての塾が"ではありません。
立派な学習塾の先生方もいますから。誤解なく。
多くの大人の方々も、「学校の先生」と言われれば「小中高校の頃の先生」を想像するでしょう。
そう、成長期・反抗期・思春期のころの目で見た先生です。
悪いイメージを持つ人や、良く思っていない人も多いことと思います。
でも、同僚として本当の先生の素顔を知ると、そのイメージは吹っ飛びます。
私は運良く、教育実習の初日の段階でそれに気付くことができました。
私たちが紹介される全校集会でのこと。
校長先生の話が始まります。
生徒達は真剣に校長先生の方を向いて話を聞いています。
もう一人の教育実習生も、校長先生を見ています。
ふと、周りの先生を見渡してみました。
誰一人校長先生を見ていません。
見ているのは生徒の様子です。
すると、サッと一人の先生が生徒の群れに入っていきました。
そこには具合が悪そうにうつむいた生徒がいました。
静かに列から引き出して、保健室へ。
プロの目を感じました。
話を聞いていない生徒はいないか、具合が悪そうな生徒はいないか、一人ひとりを見ながらいつもと何か違う感じの生徒はいないか、常に目を配っているのです。
私たちが生徒だった頃の先生も、きっと私たちの事を一生懸命見ていたのでしょう。
生徒には分からない先生方の気配りです。
職員室での会話もそうです。
生徒の前ではニコリともしない厳しく恐い先生が、先生同士の会話では満面の笑みです。
生徒が嫌いなのではありません。
生徒を正しい道しるべになりたいと考えているのです。
その先生は言いました。
「私は嫌われ役でいいと思ってる。先生方も人間だから得意不得意がある。私は生徒が正しい道を辿ってくれるなら嫌われてもいいし、怖面だから生徒指導にピッタリなんだよ。アハハ…
厳しくできる先生ばかりではないよね?でもそれで良いと思ってる。先生達皆で子どもたちを教育できれば良いんだから。子どもたちをヨシヨシしてくれる、逃げ場になるような先生だって必要なんだよ。それぞれの、役割分担ってところだね」
感動(T^T)
きっと、私が生徒だった頃の先生もこんな風に思ってくれて、育ててくれたのですね。
塾もですが、皆様も知ってください。
昨今、報道でイジメに対応しない酷い学校が出てきています。
ですが、ごく一部です。
そして、その学校の先生の中にも「どうにかしなければ!」と戦っている先生がいるはずです。
先生達は何も知らないのでも、何もしてくれないのでも、何も見ていないのでもありません。
それは私たちが生徒当時、先生の本当の姿に気付かなかっただけです。
まず、イジメ等の相談であれば、信頼置ける先生を探してください。
担任でなくていいんです。
校長、教頭、他学年の先生、保健室の先生、事務の先生…。
相談できる人はたくさんいます。
話を戻しますが、
学校では成績が良い生徒も悪い生徒も同じ時間の中で教えなければなりません。
しかも、常に新しい勉強を進めていくわけですから、「何も知らない」というのを前提に1から10まで教えなければなりません。
法律で縛られていますので、決められた学習内容を教え漏らすこともできません。
塾とは授業の性質が全く違います。
だから受験テクニックとか、特殊な解法とかを教えることはできません。
塾の先生に言わせればそれを「低レベル」と言うのかもしれませんが、そういう事を言っている人こそ教育に携わるべきではない「低レベル」な人だと思います。
是非、学校の先生のことも尊敬し、謙虚でいる塾を選んでくださいね。
それは「学校(の先生)を批判する塾」です。
そんな塾にだけは絶対に行ってはいけません。
「そんなことも教えてもらってないの!?」
「学校の先生は公務員だから適当だね!」
マスコミを鵜呑みにして「学校はイジメにも対応してくれない。塾を信じろ。」
みたいな。
それはそれは、たくさん聞きますよ。
塾と学校の両方を経験した者として言います。
「学習塾こそ、世間知らず」です。
もちろんこれも、"全ての塾が"ではありません。
立派な学習塾の先生方もいますから。誤解なく。
多くの大人の方々も、「学校の先生」と言われれば「小中高校の頃の先生」を想像するでしょう。
そう、成長期・反抗期・思春期のころの目で見た先生です。
悪いイメージを持つ人や、良く思っていない人も多いことと思います。
でも、同僚として本当の先生の素顔を知ると、そのイメージは吹っ飛びます。
私は運良く、教育実習の初日の段階でそれに気付くことができました。
私たちが紹介される全校集会でのこと。
校長先生の話が始まります。
生徒達は真剣に校長先生の方を向いて話を聞いています。
もう一人の教育実習生も、校長先生を見ています。
ふと、周りの先生を見渡してみました。
誰一人校長先生を見ていません。
見ているのは生徒の様子です。
すると、サッと一人の先生が生徒の群れに入っていきました。
そこには具合が悪そうにうつむいた生徒がいました。
静かに列から引き出して、保健室へ。
プロの目を感じました。
話を聞いていない生徒はいないか、具合が悪そうな生徒はいないか、一人ひとりを見ながらいつもと何か違う感じの生徒はいないか、常に目を配っているのです。
私たちが生徒だった頃の先生も、きっと私たちの事を一生懸命見ていたのでしょう。
生徒には分からない先生方の気配りです。
職員室での会話もそうです。
生徒の前ではニコリともしない厳しく恐い先生が、先生同士の会話では満面の笑みです。
生徒が嫌いなのではありません。
生徒を正しい道しるべになりたいと考えているのです。
その先生は言いました。
「私は嫌われ役でいいと思ってる。先生方も人間だから得意不得意がある。私は生徒が正しい道を辿ってくれるなら嫌われてもいいし、怖面だから生徒指導にピッタリなんだよ。アハハ…
厳しくできる先生ばかりではないよね?でもそれで良いと思ってる。先生達皆で子どもたちを教育できれば良いんだから。子どもたちをヨシヨシしてくれる、逃げ場になるような先生だって必要なんだよ。それぞれの、役割分担ってところだね」
感動(T^T)
きっと、私が生徒だった頃の先生もこんな風に思ってくれて、育ててくれたのですね。
塾もですが、皆様も知ってください。
昨今、報道でイジメに対応しない酷い学校が出てきています。
ですが、ごく一部です。
そして、その学校の先生の中にも「どうにかしなければ!」と戦っている先生がいるはずです。
先生達は何も知らないのでも、何もしてくれないのでも、何も見ていないのでもありません。
それは私たちが生徒当時、先生の本当の姿に気付かなかっただけです。
まず、イジメ等の相談であれば、信頼置ける先生を探してください。
担任でなくていいんです。
校長、教頭、他学年の先生、保健室の先生、事務の先生…。
相談できる人はたくさんいます。
話を戻しますが、
学校では成績が良い生徒も悪い生徒も同じ時間の中で教えなければなりません。
しかも、常に新しい勉強を進めていくわけですから、「何も知らない」というのを前提に1から10まで教えなければなりません。
法律で縛られていますので、決められた学習内容を教え漏らすこともできません。
塾とは授業の性質が全く違います。
だから受験テクニックとか、特殊な解法とかを教えることはできません。
塾の先生に言わせればそれを「低レベル」と言うのかもしれませんが、そういう事を言っている人こそ教育に携わるべきではない「低レベル」な人だと思います。
是非、学校の先生のことも尊敬し、謙虚でいる塾を選んでくださいね。
「学力」とは「問題を解く力(成績)」のことではありません。
2012年11月07日
「学力」という言葉に、送り仮名をつけてみてください。
「学ぶ力」となりますね。
一般に「学力」とは、「問題を解く力(成績)」という意味合いが強いのですが、
私は本当に学力がある人とは「学ぶ力がある人」のことだと思います。
学ぶ力があれば、今問題を解くことができなくても、問題が解けるようになれます。
分からないことがあれば調べて、読み取り、理解すれば良いのですから。
教えられなければ分からないという、学ぶ力がない人は、社会人になってから大いに苦労することでしょう。
ある場所にゴミが散乱しています。
学ぶ力がない人は「ゴミを捨てるな」という看板を立てます。
学ぶ力がある人は、ゴミ箱を設置して、「美化へのご協力ありがとうございます」という看板を立てます。
ゴミを捨ててはならないという事は、誰でも分かります。
モラルの問題です。
それでも捨てているのですから、ゴミが出やすい場所なのです。
ゴミを捨てている人の状況も、自分がゴミを片付けしなければならない状況も、ゴミをきちんと持ち帰っている人のことも考えられる人は「ゴミが散乱している」というたった1つの状況からたくさんの事を学べる人です。
「学力」とはそのような事を言うのではないでしょうか。
「学ぶ力」となりますね。
一般に「学力」とは、「問題を解く力(成績)」という意味合いが強いのですが、
私は本当に学力がある人とは「学ぶ力がある人」のことだと思います。
学ぶ力があれば、今問題を解くことができなくても、問題が解けるようになれます。
分からないことがあれば調べて、読み取り、理解すれば良いのですから。
教えられなければ分からないという、学ぶ力がない人は、社会人になってから大いに苦労することでしょう。
ある場所にゴミが散乱しています。
学ぶ力がない人は「ゴミを捨てるな」という看板を立てます。
学ぶ力がある人は、ゴミ箱を設置して、「美化へのご協力ありがとうございます」という看板を立てます。
ゴミを捨ててはならないという事は、誰でも分かります。
モラルの問題です。
それでも捨てているのですから、ゴミが出やすい場所なのです。
ゴミを捨てている人の状況も、自分がゴミを片付けしなければならない状況も、ゴミをきちんと持ち帰っている人のことも考えられる人は「ゴミが散乱している」というたった1つの状況からたくさんの事を学べる人です。
「学力」とはそのような事を言うのではないでしょうか。
タグ :学力
子どもにやる気を起こさせる方法☆
2012年11月07日
宿題をしない。
受験勉強に集中できない。
学校で寝てる。
部活もいい加減だ。
子どもにやる気を起こさせるのは大変ですww
私たちも同じ課程を経て来たのですが、棚に上げまくりで小言を言いますよね…。
さて、やる気にさせる方法はたくさんあると思いますが、人生であらゆる事に役立つ方法を1つお教えします。
同じ話を是非お子様にしてみてください。
「プラシーボ(プラセボ)」という言葉をご存知ですか?
「偽薬」のことです。
新しい頭痛によく効く薬を開発したとします。
発売するには、安全性を確かめて厚生労働省の認可をもらわなければなりません。
色々な実験を行なって、ある程度の安全性が確かめられると、次は実際に人間に試してみることになります。
これを「臨床試験」と言います。
悪く言うと人体実験です。
さて、臨床試験に付き合ってくれる同じような症状の患者さんを、例えば10名集めたとします。
5名には本物の新薬を。
残りの5名には何の効果もない偽の薬を与えます。
当然、前者の5名には効きますが、何と後者の5名の中に効く人が現れるのです!
これを「プラシーボ効果」と言います。
「良い薬を手に入れた!やった!これで治るんだ!」と信じ込んだことで、人間に元々備わった自己治癒力が活性化して治ってしまうのです。
これは、医療の世界では当たり前に知られた話です。
このプラシーボ効果を使って、手術ができない脳腫瘍を治療する方法が行なわれている国(病院)もあるようです。
大学時代に聞いた実例では、手の施しようが内末期ガン患者が告知された後に「オレはガンなんかで死ぬ人間じゃない!絶対治してやる!!」と強く思っただけで、ガンが縮小したという話があります。
健康食品や栄養ドリンクが効いたような気がするのもプラシーボ効果です。
実は、人間は考えられないような力を元々持っています。
普段は発揮できないだけなのです。
スポーツでは「イメージトレーニング」というのが昔から行なわれています。
これもプラシーボ効果を発揮する方法です。
上手くいく様子をイメージし、周りの歓声やその後の活躍する姿を想像するのです。
「○○高校に行ったら、あんなことやこんな事をしよう。きっと彼女もできるぞ~!」なんて、想像してみるときっとワクワクすることでしょう。
このワクワクする気持ちを大切にすれば、やる気に満ち溢れてきます。
逆に「自分にはできない」「ダメだ」と思ったら、本当にダメになってしまいます。
「勉強せんと合格できんよ!私立には行かせんけんね!!」とか、精神をマイナス方向に持っていく小言はやめましょう。
「頑張れ!」も、重荷になったり、他人事に聞こえたりします。
常に良いイメージを連想する方向に持っていってください。
「あなたは歩き始めるのが早かったのよ。何でも覚えが早くて。だから、受験も大丈夫。焦らずにね」と、周りの人もそんな言葉かけをすると、本人のサポートになると思います。
ただし、この良いイメージが妄想で終わらないように…。
受験勉強に集中できない。
学校で寝てる。
部活もいい加減だ。
子どもにやる気を起こさせるのは大変ですww
私たちも同じ課程を経て来たのですが、棚に上げまくりで小言を言いますよね…。
さて、やる気にさせる方法はたくさんあると思いますが、人生であらゆる事に役立つ方法を1つお教えします。
同じ話を是非お子様にしてみてください。
「プラシーボ(プラセボ)」という言葉をご存知ですか?
「偽薬」のことです。
新しい頭痛によく効く薬を開発したとします。
発売するには、安全性を確かめて厚生労働省の認可をもらわなければなりません。
色々な実験を行なって、ある程度の安全性が確かめられると、次は実際に人間に試してみることになります。
これを「臨床試験」と言います。
悪く言うと人体実験です。
さて、臨床試験に付き合ってくれる同じような症状の患者さんを、例えば10名集めたとします。
5名には本物の新薬を。
残りの5名には何の効果もない偽の薬を与えます。
当然、前者の5名には効きますが、何と後者の5名の中に効く人が現れるのです!
これを「プラシーボ効果」と言います。
「良い薬を手に入れた!やった!これで治るんだ!」と信じ込んだことで、人間に元々備わった自己治癒力が活性化して治ってしまうのです。
これは、医療の世界では当たり前に知られた話です。
このプラシーボ効果を使って、手術ができない脳腫瘍を治療する方法が行なわれている国(病院)もあるようです。
大学時代に聞いた実例では、手の施しようが内末期ガン患者が告知された後に「オレはガンなんかで死ぬ人間じゃない!絶対治してやる!!」と強く思っただけで、ガンが縮小したという話があります。
健康食品や栄養ドリンクが効いたような気がするのもプラシーボ効果です。
実は、人間は考えられないような力を元々持っています。
普段は発揮できないだけなのです。
スポーツでは「イメージトレーニング」というのが昔から行なわれています。
これもプラシーボ効果を発揮する方法です。
上手くいく様子をイメージし、周りの歓声やその後の活躍する姿を想像するのです。
「○○高校に行ったら、あんなことやこんな事をしよう。きっと彼女もできるぞ~!」なんて、想像してみるときっとワクワクすることでしょう。
このワクワクする気持ちを大切にすれば、やる気に満ち溢れてきます。
逆に「自分にはできない」「ダメだ」と思ったら、本当にダメになってしまいます。
「勉強せんと合格できんよ!私立には行かせんけんね!!」とか、精神をマイナス方向に持っていく小言はやめましょう。
「頑張れ!」も、重荷になったり、他人事に聞こえたりします。
常に良いイメージを連想する方向に持っていってください。
「あなたは歩き始めるのが早かったのよ。何でも覚えが早くて。だから、受験も大丈夫。焦らずにね」と、周りの人もそんな言葉かけをすると、本人のサポートになると思います。
ただし、この良いイメージが妄想で終わらないように…。
視力と学力と中学生の脅威の集中力。
2012年11月07日
最近、お子様が目を細めて遠くを見ることはないでしょうか?
ならば、すぐにメガネなりコンタクトを作られる事をお勧めします。
視力が落ちると学力が必ずと言っていいほど低下します。
私は中学の頃に視力が落ち始めました。
大好きな理科の授業だったら、黒板丸ごと写真のように覚えていましたし、先生の言葉も録音したように覚えていました。
定期テストの問題を解くとき、「あ、この答えはあの時の授業で、黒板の右下に書いてあったなぁ」とか、覚えていたものです。
ところがある時、その能力が落ち始めました。
後から気付いたのは同時に視力が落ちていたことです。
黒板が見にくくなり、ノートに書き写すことに集中力が奪われ、先生の話が耳に入りにくくなっていました。
事実、私の教え子も視力が落ちると同時に学力が落ちることが非常に多いのです。
中学生の集中力は人生の中で最も高いと言われます。
小学生は雑念が多いと言ったらいいのでしょうか?
大人に比べれば物事をどんどん吸収するのかもしれませんが、色々な事に興味を持ち、キョロキョロしたり手遊びしたり…。
脳の発達が完了し、少し大人になって落ち着きを持ち、基礎学力や常識が備わったことで色々なことが分かるようになった中学生の時期が、実は最も集中できるのです。
高校生~大人になればなるほど、その集中力は低下していきます。
この集中力が手に入るのは今だけです。
できるだけ早く視力をサポートしてあげてくださいね。
ならば、すぐにメガネなりコンタクトを作られる事をお勧めします。
視力が落ちると学力が必ずと言っていいほど低下します。
私は中学の頃に視力が落ち始めました。
大好きな理科の授業だったら、黒板丸ごと写真のように覚えていましたし、先生の言葉も録音したように覚えていました。
定期テストの問題を解くとき、「あ、この答えはあの時の授業で、黒板の右下に書いてあったなぁ」とか、覚えていたものです。
ところがある時、その能力が落ち始めました。
後から気付いたのは同時に視力が落ちていたことです。
黒板が見にくくなり、ノートに書き写すことに集中力が奪われ、先生の話が耳に入りにくくなっていました。
事実、私の教え子も視力が落ちると同時に学力が落ちることが非常に多いのです。
中学生の集中力は人生の中で最も高いと言われます。
小学生は雑念が多いと言ったらいいのでしょうか?
大人に比べれば物事をどんどん吸収するのかもしれませんが、色々な事に興味を持ち、キョロキョロしたり手遊びしたり…。
脳の発達が完了し、少し大人になって落ち着きを持ち、基礎学力や常識が備わったことで色々なことが分かるようになった中学生の時期が、実は最も集中できるのです。
高校生~大人になればなるほど、その集中力は低下していきます。
この集中力が手に入るのは今だけです。
できるだけ早く視力をサポートしてあげてくださいね。
1たす1はなぜ2になるの?
2012年11月07日
「1+1=2」
幼児でも知っている計算です。
発明家エジソンが子どもの頃「1たす1はなぜ2になるの?」と先生に質問したというエピソードはあまりにも有名です。
例えば、2つのコップについだジュースを1つにまとめれば、1+1=1になります。
ある作業を1人ではなく2人で協力してやれば、その効率的には3人分の作業量になる、つまり1+1=3かもしれません。
屁理屈に聞こえるかもしれませんが、これは科学でもとても大切なことです。
当たり前の事を当たり前と捉えないこと。
理科の教科書に書いてある事象も、実は間違っているかもしれません。
「理科=暗記科目」という考え方は古過ぎます。
用語は全く重要ではありません。(もちろんテストでは用語を聞かれますが)
その事象がなぜそうなるのかを考えることが「科学すること」です。
その考えが正しい事を確かめようとする行為が「実験すること」です。
知的好奇心の塊なのが「理科」なのです。
だから、色々な事を考えて楽しんで欲しい教科です。
理科の点数が良くなくても、このような物の見方が育っている人は、きっと科学者に向いているでしょうね。
さて、大学の数学科では、1+1がなぜ2になるのかを、論文で書き示したり、証明を行なうこともあります。
そこでは、1の定義から示さなければなりません。
1の定義が変われば、2にはならないことばかりなのです。
世の中を様々な側面から見て、様々な考察を持ち、様々な確認を行なうこと。
固執した考え方ではなく、柔軟な思考を持って世の中を見ると、世界が違って見えるかもしれません。
幼児でも知っている計算です。
発明家エジソンが子どもの頃「1たす1はなぜ2になるの?」と先生に質問したというエピソードはあまりにも有名です。
例えば、2つのコップについだジュースを1つにまとめれば、1+1=1になります。
ある作業を1人ではなく2人で協力してやれば、その効率的には3人分の作業量になる、つまり1+1=3かもしれません。
屁理屈に聞こえるかもしれませんが、これは科学でもとても大切なことです。
当たり前の事を当たり前と捉えないこと。
理科の教科書に書いてある事象も、実は間違っているかもしれません。
「理科=暗記科目」という考え方は古過ぎます。
用語は全く重要ではありません。(もちろんテストでは用語を聞かれますが)
その事象がなぜそうなるのかを考えることが「科学すること」です。
その考えが正しい事を確かめようとする行為が「実験すること」です。
知的好奇心の塊なのが「理科」なのです。
だから、色々な事を考えて楽しんで欲しい教科です。
理科の点数が良くなくても、このような物の見方が育っている人は、きっと科学者に向いているでしょうね。
さて、大学の数学科では、1+1がなぜ2になるのかを、論文で書き示したり、証明を行なうこともあります。
そこでは、1の定義から示さなければなりません。
1の定義が変われば、2にはならないことばかりなのです。
世の中を様々な側面から見て、様々な考察を持ち、様々な確認を行なうこと。
固執した考え方ではなく、柔軟な思考を持って世の中を見ると、世界が違って見えるかもしれません。
ゆとり教育。
2012年11月06日
ゆとり教育が終了しました。
特に大きな変化があったのは、理科・数学の学習内容と学習時間の増加です。
前の記事にも書いたように、日本国は子どもたちに日本の科学技術を背負ってもらいたいということです。
さて、「ゆとり教育」とはなんだったのでしょう?
ねらいそのものは良いものだったと思います。
学校現場がゆとりの時間を利用して、独自の取り組みができ、子どもたちに様々な体験・経験をさせられるからです。
ですが、方法がまずかった。
学校現場に丸投げ。
現場の先生達は「何をしろって言うんだ!?」って感じだったでしょう。
面倒な先生は、教科書どおりの授業だけをしたはずです。
ゆとりの時間も大したことをしない学校もあったでしょう。
国が決めた学習内容、つまり教科書通りの事をすれば任務完了ですから。
一生懸命な先生や学校に出会っていれば、ゆとり教育も意義があったでしょう。
でも、公務員ですから、最低限のことだけをやっていた先生・学校が多かったでしょう。
先生達も議論はしていましたが、国がある程度の具体的な方針を打ち出さなければ決着が付きません。
ゆとり教育はこうして崩壊するしかなかったのですね。
似た様なものに、絶対評価があります。
つまり、生徒個人の目標を満足に達成したとすれば、全員に5をあげても良いというものです。
同じ80点でも、子どもによってその重みが違うからです。
昔は5は○人まで。という決まりがありました。
基準が曖昧で、学校によって成績の付け方に差があります。
ある中学校では5がたくさんいて、別の中学校では5があまりいないってこともあります。
困ったのは高校受験です。
絶対評価で中学校ごとの基準が違うにも関わらず、同じように比較して合否を決定するのです。
だから、成績の付け方が厳しい学校は保護者からのクレームを受けることになりました。
これは高校側の工夫で改善する方向に行っています。
最近の政治は特にそうですが、もっと国が指導力を発揮しなければならないと痛感する事例でした。
特に大きな変化があったのは、理科・数学の学習内容と学習時間の増加です。
前の記事にも書いたように、日本国は子どもたちに日本の科学技術を背負ってもらいたいということです。
さて、「ゆとり教育」とはなんだったのでしょう?
ねらいそのものは良いものだったと思います。
学校現場がゆとりの時間を利用して、独自の取り組みができ、子どもたちに様々な体験・経験をさせられるからです。
ですが、方法がまずかった。
学校現場に丸投げ。
現場の先生達は「何をしろって言うんだ!?」って感じだったでしょう。
面倒な先生は、教科書どおりの授業だけをしたはずです。
ゆとりの時間も大したことをしない学校もあったでしょう。
国が決めた学習内容、つまり教科書通りの事をすれば任務完了ですから。
一生懸命な先生や学校に出会っていれば、ゆとり教育も意義があったでしょう。
でも、公務員ですから、最低限のことだけをやっていた先生・学校が多かったでしょう。
先生達も議論はしていましたが、国がある程度の具体的な方針を打ち出さなければ決着が付きません。
ゆとり教育はこうして崩壊するしかなかったのですね。
似た様なものに、絶対評価があります。
つまり、生徒個人の目標を満足に達成したとすれば、全員に5をあげても良いというものです。
同じ80点でも、子どもによってその重みが違うからです。
昔は5は○人まで。という決まりがありました。
基準が曖昧で、学校によって成績の付け方に差があります。
ある中学校では5がたくさんいて、別の中学校では5があまりいないってこともあります。
困ったのは高校受験です。
絶対評価で中学校ごとの基準が違うにも関わらず、同じように比較して合否を決定するのです。
だから、成績の付け方が厳しい学校は保護者からのクレームを受けることになりました。
これは高校側の工夫で改善する方向に行っています。
最近の政治は特にそうですが、もっと国が指導力を発揮しなければならないと痛感する事例でした。
「理科離れ」は「理科離れ」ではない。
2012年11月06日
矛盾するタイトルですが。
私は「理科離れ」は「理科の基礎知識量の低下」だと考えています。
ちなみに「学力の低下」でもありません。
「理科離れ」という言葉はきっと国策でしょう。
中学教員時代の話です。
「理科が好きな人、手を上げて」という問いに、80%以上の生徒が手を上げます。
「実験が好きな人、手を上げて」という問いに、98%以上の生徒が手を上げます。
学校現場の理科教員が「理科離れ」を感じている人間はほとんどいないのではないでしょうか?
たしかに、観察力や考察力、洞察力がどうかと問われれば、能力が高い生徒は少ないかもしれません。
でも、昔から比べてどうかと聞かれれば「中学生ならその程度」と感じると思います。
「好きこそものの上手なれ」という言葉もあります。
本当に理科から離れてしまったのでしょうか?
ゆとり教育が終了しました。
ゆとり教育については別の記事にするとして、
この教育では理数系の学習内容が大幅に削られました。
もちろん、小学校から高校まですべて。
おのずと、大学入学時の理科の知識量が減ります。
学力が低下したのではなく、学習内容が少ないので、知識量が減っただけです。
大学でも基礎科学から教える時間が必要になり、結果、日本全体の科学技術発展が停滞する事態になりました。
特に今、中国や韓国の産業が活発で、日本の企業が追い抜かれています。
先日のニュースでは、液晶テレビ業界の世界シェアの1位はサムスン(韓国)、2位はLG(韓国)、3位にようやく世界のSONYという有り様です。
日本は国土が狭く、農業・漁業・畜産などの生産や、石油などの資源に乏しい国です。
輸出による利益が望めません。
代わりに、日本人という人種特有の手先の器用さや丁寧さで、科学技術を提供するのが世界における日本の役割でした。
これが他国にとって代わられると、大変なことになります。
だから「理科離れ」という言葉を発したのです。
理系に興味を持ってもらい、科学技術に寄与する人を育てたいのです。
子どもたちが大好きな科学実験を上手く使わない手はありません。
科学実験は日本の未来を切り開く原動力だと考えています。
私は「理科離れ」は「理科の基礎知識量の低下」だと考えています。
ちなみに「学力の低下」でもありません。
「理科離れ」という言葉はきっと国策でしょう。
中学教員時代の話です。
「理科が好きな人、手を上げて」という問いに、80%以上の生徒が手を上げます。
「実験が好きな人、手を上げて」という問いに、98%以上の生徒が手を上げます。
学校現場の理科教員が「理科離れ」を感じている人間はほとんどいないのではないでしょうか?
たしかに、観察力や考察力、洞察力がどうかと問われれば、能力が高い生徒は少ないかもしれません。
でも、昔から比べてどうかと聞かれれば「中学生ならその程度」と感じると思います。
「好きこそものの上手なれ」という言葉もあります。
本当に理科から離れてしまったのでしょうか?
ゆとり教育が終了しました。
ゆとり教育については別の記事にするとして、
この教育では理数系の学習内容が大幅に削られました。
もちろん、小学校から高校まですべて。
おのずと、大学入学時の理科の知識量が減ります。
学力が低下したのではなく、学習内容が少ないので、知識量が減っただけです。
大学でも基礎科学から教える時間が必要になり、結果、日本全体の科学技術発展が停滞する事態になりました。
特に今、中国や韓国の産業が活発で、日本の企業が追い抜かれています。
先日のニュースでは、液晶テレビ業界の世界シェアの1位はサムスン(韓国)、2位はLG(韓国)、3位にようやく世界のSONYという有り様です。
日本は国土が狭く、農業・漁業・畜産などの生産や、石油などの資源に乏しい国です。
輸出による利益が望めません。
代わりに、日本人という人種特有の手先の器用さや丁寧さで、科学技術を提供するのが世界における日本の役割でした。
これが他国にとって代わられると、大変なことになります。
だから「理科離れ」という言葉を発したのです。
理系に興味を持ってもらい、科学技術に寄与する人を育てたいのです。
子どもたちが大好きな科学実験を上手く使わない手はありません。
科学実験は日本の未来を切り開く原動力だと考えています。
子の疑問への親の答え方。
2012年11月06日
「どうして空って青いの?」
だれでも、子どもの頃に抱いた疑問かもしれません。
次から次に質問をしてくる時期があります。
答えを知っているなら良いのですが、知らなかったり、あまりの質問の多さに「しらん!」「うるさい!」「後でね…」「…(無視)」という感じになってしまうことがありますね。
でも、このような質問が出てくるのは「知的好奇心」が高いからです。
知的好奇心を維持できれば、大きくなって「勉強しなさい!」「宿題やったの!?」なんて小言がいらなくなるかもしれません。
私たち大人も、子どもの頃に勉強が「楽しかった」「好きだった」と言えるのは極少数でしょう。
でも、大人になってからようやく勉強の必要性を知り、自分の事を棚に上げて「勉強しなさい!」って言ってしまいます。
子どもたちはゲームが得意です。
最近はポータブルゲームが普及し、どこででもゲームをやっている子どもを見かけます。
買い物中、外食中、道端に座り込んで…。
勉強もこのくらい集中してくれれば…って思ってしまいますね。
さて、ゲームでは子どもたちは多くの特殊用語を覚え、技術を駆使して次々に難題をクリアしていきます。
そう、自学自習して自己解決しているのです。
勉強が得意でない子も、ゲームは得意だったりします。
勉強も同じように楽しさを知れば、きっとできるようになるのです。
だから、その知的好奇心を削いではいけません。
分からない事は「お母さん(お父さん)も分からないよ。そんなことに気付くなんてすごいね!大きくなったら調べてみたら?(インターネットで調べてみるね)」とか、少し大きな子なら「自分で調べてみたら?」とか、「知りたいという意欲」に繋げてみてください。
それも大切な勉強だと思います。
せっかく子どもたちが「勉強したい」と言っているのに、「知らん!」と言うなら、「勉強をするな」と言っているようなものです。
勉強したいオーラを消さず、大切にしてあげてください。
私が開く科学実験教室は、このような子どもの知的好奇心を大切に育てる事を目的としています。
だれでも、子どもの頃に抱いた疑問かもしれません。
次から次に質問をしてくる時期があります。
答えを知っているなら良いのですが、知らなかったり、あまりの質問の多さに「しらん!」「うるさい!」「後でね…」「…(無視)」という感じになってしまうことがありますね。
でも、このような質問が出てくるのは「知的好奇心」が高いからです。
知的好奇心を維持できれば、大きくなって「勉強しなさい!」「宿題やったの!?」なんて小言がいらなくなるかもしれません。
私たち大人も、子どもの頃に勉強が「楽しかった」「好きだった」と言えるのは極少数でしょう。
でも、大人になってからようやく勉強の必要性を知り、自分の事を棚に上げて「勉強しなさい!」って言ってしまいます。
子どもたちはゲームが得意です。
最近はポータブルゲームが普及し、どこででもゲームをやっている子どもを見かけます。
買い物中、外食中、道端に座り込んで…。
勉強もこのくらい集中してくれれば…って思ってしまいますね。
さて、ゲームでは子どもたちは多くの特殊用語を覚え、技術を駆使して次々に難題をクリアしていきます。
そう、自学自習して自己解決しているのです。
勉強が得意でない子も、ゲームは得意だったりします。
勉強も同じように楽しさを知れば、きっとできるようになるのです。
だから、その知的好奇心を削いではいけません。
分からない事は「お母さん(お父さん)も分からないよ。そんなことに気付くなんてすごいね!大きくなったら調べてみたら?(インターネットで調べてみるね)」とか、少し大きな子なら「自分で調べてみたら?」とか、「知りたいという意欲」に繋げてみてください。
それも大切な勉強だと思います。
せっかく子どもたちが「勉強したい」と言っているのに、「知らん!」と言うなら、「勉強をするな」と言っているようなものです。
勉強したいオーラを消さず、大切にしてあげてください。
私が開く科学実験教室は、このような子どもの知的好奇心を大切に育てる事を目的としています。