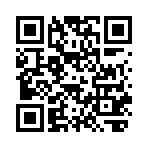1たす1はなぜ2になるの?
2012年11月07日
「1+1=2」
幼児でも知っている計算です。
発明家エジソンが子どもの頃「1たす1はなぜ2になるの?」と先生に質問したというエピソードはあまりにも有名です。
例えば、2つのコップについだジュースを1つにまとめれば、1+1=1になります。
ある作業を1人ではなく2人で協力してやれば、その効率的には3人分の作業量になる、つまり1+1=3かもしれません。
屁理屈に聞こえるかもしれませんが、これは科学でもとても大切なことです。
当たり前の事を当たり前と捉えないこと。
理科の教科書に書いてある事象も、実は間違っているかもしれません。
「理科=暗記科目」という考え方は古過ぎます。
用語は全く重要ではありません。(もちろんテストでは用語を聞かれますが)
その事象がなぜそうなるのかを考えることが「科学すること」です。
その考えが正しい事を確かめようとする行為が「実験すること」です。
知的好奇心の塊なのが「理科」なのです。
だから、色々な事を考えて楽しんで欲しい教科です。
理科の点数が良くなくても、このような物の見方が育っている人は、きっと科学者に向いているでしょうね。
さて、大学の数学科では、1+1がなぜ2になるのかを、論文で書き示したり、証明を行なうこともあります。
そこでは、1の定義から示さなければなりません。
1の定義が変われば、2にはならないことばかりなのです。
世の中を様々な側面から見て、様々な考察を持ち、様々な確認を行なうこと。
固執した考え方ではなく、柔軟な思考を持って世の中を見ると、世界が違って見えるかもしれません。
幼児でも知っている計算です。
発明家エジソンが子どもの頃「1たす1はなぜ2になるの?」と先生に質問したというエピソードはあまりにも有名です。
例えば、2つのコップについだジュースを1つにまとめれば、1+1=1になります。
ある作業を1人ではなく2人で協力してやれば、その効率的には3人分の作業量になる、つまり1+1=3かもしれません。
屁理屈に聞こえるかもしれませんが、これは科学でもとても大切なことです。
当たり前の事を当たり前と捉えないこと。
理科の教科書に書いてある事象も、実は間違っているかもしれません。
「理科=暗記科目」という考え方は古過ぎます。
用語は全く重要ではありません。(もちろんテストでは用語を聞かれますが)
その事象がなぜそうなるのかを考えることが「科学すること」です。
その考えが正しい事を確かめようとする行為が「実験すること」です。
知的好奇心の塊なのが「理科」なのです。
だから、色々な事を考えて楽しんで欲しい教科です。
理科の点数が良くなくても、このような物の見方が育っている人は、きっと科学者に向いているでしょうね。
さて、大学の数学科では、1+1がなぜ2になるのかを、論文で書き示したり、証明を行なうこともあります。
そこでは、1の定義から示さなければなりません。
1の定義が変われば、2にはならないことばかりなのです。
世の中を様々な側面から見て、様々な考察を持ち、様々な確認を行なうこと。
固執した考え方ではなく、柔軟な思考を持って世の中を見ると、世界が違って見えるかもしれません。