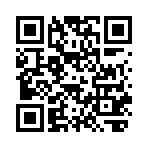スポンサーサイト
子どもに勉強させる方法4【連載】
2012年12月12日
子どもに勉強させる方法を連載中です。
本記事は第四回目。
始めから読みたい方はこちらへ。
「子どもに勉強させる方法」
4.未来の設計図
さあ、具体的にどうすれば子どもが勉強してくれるのか。その内容に入っていきます。
私は理科の教師をしています。どの教科でもそうですが、特に理科という教科は授業の最初で行なう「導入」を重視します。導入を失敗すれば、その授業丸々一時間が失敗に終わることも多いからです。
さて、導入というのは「さて前回の授業では、2つ以上の物質が合わさる化学変化『化合』を勉強しましたね。では、その逆。1つの物質が2つ以上に分かれる化学変化もあるはずです。今日はそれを実験で確かめてみましょう」などという、「今日はこの勉強をするよ」と示すことです。これで子どもたちは「分かれる反応の実験」という背景を把握し興味を持つことで、その日の授業の内容が吸収しやすくなるのです。。
ところが、言い回しが悪かったりして、今一つ説明し切れていないと、何の勉強をしているのか、何の実験をしているのかを全く理解しないまま、闇雲に黒板を写し、実験をし、無駄な時間を過ごすことになります。
これは授業だけでなく何にでも共通することです。人間の行動には理由があります。例えば、ただ「掃除しろ」と言われて納得しないままやるよりも、やれば周りの人が喜ぶんだとか、気持ちよく過ごせて勉強がはかどるんだとか、意義を見出させることが大変重要なのです。つまり、「動機」です。
子どもに勉強をさせたいならば、まずは勉強しようと思える「動機」作りをしなければならないのです。時間がかかってしまっても構いません。大切なことですから、しっかり動機付けしていきましょう。
本記事は第四回目。
始めから読みたい方はこちらへ。
「子どもに勉強させる方法」
4.未来の設計図
さあ、具体的にどうすれば子どもが勉強してくれるのか。その内容に入っていきます。
私は理科の教師をしています。どの教科でもそうですが、特に理科という教科は授業の最初で行なう「導入」を重視します。導入を失敗すれば、その授業丸々一時間が失敗に終わることも多いからです。
さて、導入というのは「さて前回の授業では、2つ以上の物質が合わさる化学変化『化合』を勉強しましたね。では、その逆。1つの物質が2つ以上に分かれる化学変化もあるはずです。今日はそれを実験で確かめてみましょう」などという、「今日はこの勉強をするよ」と示すことです。これで子どもたちは「分かれる反応の実験」という背景を把握し興味を持つことで、その日の授業の内容が吸収しやすくなるのです。。
ところが、言い回しが悪かったりして、今一つ説明し切れていないと、何の勉強をしているのか、何の実験をしているのかを全く理解しないまま、闇雲に黒板を写し、実験をし、無駄な時間を過ごすことになります。
これは授業だけでなく何にでも共通することです。人間の行動には理由があります。例えば、ただ「掃除しろ」と言われて納得しないままやるよりも、やれば周りの人が喜ぶんだとか、気持ちよく過ごせて勉強がはかどるんだとか、意義を見出させることが大変重要なのです。つまり、「動機」です。
子どもに勉強をさせたいならば、まずは勉強しようと思える「動機」作りをしなければならないのです。時間がかかってしまっても構いません。大切なことですから、しっかり動機付けしていきましょう。
子どもに勉強させる方法3【連載】
2012年12月12日
子どもに勉強させる方法を連載中です。
本記事は第三回目。
始めから読みたい方はこちらへ。
「子どもに勉強させる方法」
3.我の振りを見て、子の振り直せ
あなたは子どもの頃、どのような子どもだったでしょうか?ちょっと思い出してみてください。
宿題はきちんとやっていましたか?宿題以外の家庭学習もやっていましたか?学校の授業は真面目に受けていましたか?遅刻はしませんでしたか?忘れ物はしていませんでしたか?部活はサボったことがありませんか?親の手伝いをしていましたか?おもちゃの片付けをきちんとしていましたか?早寝早起きをしていましたか?お小遣いの使い方は有意義なものでしたか?自分できちんと体調管理をしていましたか?親や先生や友だちに嘘はつきませんでしたか?友だちとは仲良くやっていましたか?親孝行だと思いますか?赤信号を渡った事はありませんか?自分が悪いと思いつつ、人を責めたことはありませんか?
全てにYESで答えられる人なんていません。私だって先生という職業をしつつ、こんな書物を書きつつ、NOの方が多いですよ。
ところが、あなたの子どもがこの質問にNOとなる行動をしたら、きっとあなたは子どもを叱責するのではないでしょうか。いえ、それが悪いとは言いません。子どもに同じ過ちをして欲しくないという思い、正しい道を示したいという思いは、どの親にも共通することであり、必要なことです。ですがいつの間にか、自分の事を棚に上げっぱなしで、完全に仕舞い込んでしまっていないでしょうか。
子どもには、父親と母親の遺伝子が半分ずつ入っています。つまり、父親と母親の分身であるわけです。性格というものは先天的な部分と後天的な部分があります。また、隔世遺伝と言って、祖父母の特徴が現れることもありますから、父親と母親にに完全に一致するわけではありませんし、足して二で割るような簡単なものでもありません。でも、ベースとなるものは近いものを持っているはずですし、祖父母が育てたあなたが育てているのですから、生活環境も似ているわけです。つまり、あなたが子どもの頃に経験した悪い事・後ろめたいことは、あなたの子どもも経験する可能性が高いのです。
もしあなたが子どもに勉強させたいと思うのなら、自分だったらどうすれば勉強したいと思うのかを考えてみましょう。
まずはあなたが子どもの頃どうだったのかを思い出すことから始めましょう。この機会に、ご自身の事を客観的にしっかり見つめてみてください。
本記事は第三回目。
始めから読みたい方はこちらへ。
「子どもに勉強させる方法」
3.我の振りを見て、子の振り直せ
あなたは子どもの頃、どのような子どもだったでしょうか?ちょっと思い出してみてください。
宿題はきちんとやっていましたか?宿題以外の家庭学習もやっていましたか?学校の授業は真面目に受けていましたか?遅刻はしませんでしたか?忘れ物はしていませんでしたか?部活はサボったことがありませんか?親の手伝いをしていましたか?おもちゃの片付けをきちんとしていましたか?早寝早起きをしていましたか?お小遣いの使い方は有意義なものでしたか?自分できちんと体調管理をしていましたか?親や先生や友だちに嘘はつきませんでしたか?友だちとは仲良くやっていましたか?親孝行だと思いますか?赤信号を渡った事はありませんか?自分が悪いと思いつつ、人を責めたことはありませんか?
全てにYESで答えられる人なんていません。私だって先生という職業をしつつ、こんな書物を書きつつ、NOの方が多いですよ。
ところが、あなたの子どもがこの質問にNOとなる行動をしたら、きっとあなたは子どもを叱責するのではないでしょうか。いえ、それが悪いとは言いません。子どもに同じ過ちをして欲しくないという思い、正しい道を示したいという思いは、どの親にも共通することであり、必要なことです。ですがいつの間にか、自分の事を棚に上げっぱなしで、完全に仕舞い込んでしまっていないでしょうか。
子どもには、父親と母親の遺伝子が半分ずつ入っています。つまり、父親と母親の分身であるわけです。性格というものは先天的な部分と後天的な部分があります。また、隔世遺伝と言って、祖父母の特徴が現れることもありますから、父親と母親にに完全に一致するわけではありませんし、足して二で割るような簡単なものでもありません。でも、ベースとなるものは近いものを持っているはずですし、祖父母が育てたあなたが育てているのですから、生活環境も似ているわけです。つまり、あなたが子どもの頃に経験した悪い事・後ろめたいことは、あなたの子どもも経験する可能性が高いのです。
もしあなたが子どもに勉強させたいと思うのなら、自分だったらどうすれば勉強したいと思うのかを考えてみましょう。
まずはあなたが子どもの頃どうだったのかを思い出すことから始めましょう。この機会に、ご自身の事を客観的にしっかり見つめてみてください。
子どもに勉強させる方法2【連載】
2012年12月12日
子どもに勉強させる方法を連載中です。
本記事は第二回目。
始めから読みたい方はこちらへ。
「子どもに勉強させる方法」
2.教科学習への転化
なるほど、一般的に言う勉強もテレビゲームも同じ性質である事は分かった。では、なぜテレビゲームは一生懸命やるのに、勉強はやらないのか。
この答えはかんたんですね。「楽しい」か「楽しくない」か、です。
テレビゲームが楽しいのは、クリアした達成感やクリアしたときに現れる素晴らしい映像があるから。そこでしか得られない特別なアイテムがあるから。きっと待っているであろう、素晴らしいエンディングがあるから。友だちより早くクリアしたという優越感に浸れるから。そういったものが子どもたちがテレビゲームに誘われる原動力となっているのです。
そもそもテレビゲームを作る会社は、ビジネスとしてそのゲームが売れて欲しいわけですから、子どもたちが楽しめるようにたくさんの「仕掛け」を必死で考えています。例えクリアできなくても、やること自体に楽しみを見出せるように様々な工夫が凝らしてあります。見えない心理作戦があるのです。
つまり、教科学習もテレビゲームに習って教科学習をさせようという「仕掛け」を準備できれば、子どもたちは率先して勉強できるようになるはずです。
教科書は進化しました。昔の教科書に比べてフルカラーになり、挿絵も多くなり、身近な話題も掲載され、より子どもたちの興味を引くような作りです。しかし、まだ弱い。問題が解けたときに素晴らしい映像が見られるわけでもありませんし、何か特別な物がもらえるわけでもありません。そもそも、学問にはエンディングなんてありません。ですから、学校の先生・塾の先生、そして親が何らかの素晴らしい「仕掛け」を準備してあげる必要があるのです。
ただし、後に述べることですが、間違っても「今度のテストで八十点以上とったら、あのゲームを買ってあげる」などという安易な方法は感心しません。大切なことですので先に言っておきます。
本記事は第二回目。
始めから読みたい方はこちらへ。
「子どもに勉強させる方法」
2.教科学習への転化
なるほど、一般的に言う勉強もテレビゲームも同じ性質である事は分かった。では、なぜテレビゲームは一生懸命やるのに、勉強はやらないのか。
この答えはかんたんですね。「楽しい」か「楽しくない」か、です。
テレビゲームが楽しいのは、クリアした達成感やクリアしたときに現れる素晴らしい映像があるから。そこでしか得られない特別なアイテムがあるから。きっと待っているであろう、素晴らしいエンディングがあるから。友だちより早くクリアしたという優越感に浸れるから。そういったものが子どもたちがテレビゲームに誘われる原動力となっているのです。
そもそもテレビゲームを作る会社は、ビジネスとしてそのゲームが売れて欲しいわけですから、子どもたちが楽しめるようにたくさんの「仕掛け」を必死で考えています。例えクリアできなくても、やること自体に楽しみを見出せるように様々な工夫が凝らしてあります。見えない心理作戦があるのです。
つまり、教科学習もテレビゲームに習って教科学習をさせようという「仕掛け」を準備できれば、子どもたちは率先して勉強できるようになるはずです。
教科書は進化しました。昔の教科書に比べてフルカラーになり、挿絵も多くなり、身近な話題も掲載され、より子どもたちの興味を引くような作りです。しかし、まだ弱い。問題が解けたときに素晴らしい映像が見られるわけでもありませんし、何か特別な物がもらえるわけでもありません。そもそも、学問にはエンディングなんてありません。ですから、学校の先生・塾の先生、そして親が何らかの素晴らしい「仕掛け」を準備してあげる必要があるのです。
ただし、後に述べることですが、間違っても「今度のテストで八十点以上とったら、あのゲームを買ってあげる」などという安易な方法は感心しません。大切なことですので先に言っておきます。