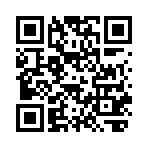スポンサーサイト
不老不死の科学。
2012年11月19日
大昔から、多くの者が望んできた不老不死。
実現してしまったら、不老不死の本人は苦しむ結果になるのかもしれませんが、
「寿命」というものは科学的に解明されつつあります。
さて、ベニクラゲというクラゲがいます。
「不老」ではありませんが「不死」とは呼べるかもしれません。
一度、老化を辿りますが、死ぬ寸前に若返り始め、生まれた頃にリセットされる驚きの生物です。
もちろん、物理的に殺してしまえば死んでしまうので、完全なる不死ではありません。
私は遺伝子工学が専門ですが、この系統の人間なら寿命を決めるものは誰でも知っています。
「テロメア」と呼ばれる、染色体(DNA)の両端の部位です。
若い細胞というのは細胞分裂を盛んに行ない、新しい細胞を生み出します。
ところが、細胞分裂はどれだけでも起きる訳ではなく、限度回数があります。
この限度回数を決めているのが「テロメア」だろうと言われています。
細胞分裂を繰り返す度に、テロメアという部位は短くなっていきます。
テロメアがなくなってしまった細胞は、それ以上分裂することがなくなります。
こうなると、その細胞自身の寿命までで終わり。
あとは死に向かうしかありません。
細胞死が増えれば、体中の器官は不調をきたし、生命を維持できなくなります。
ということは、テロメアをどうにか伸ばすことができれば、細胞分裂を復活させられ、生命を維持することができるようになります。
「テロメアの長さを維持すること」が不老不死につながるのです。
といっても、体中の全ての細胞のテロメアを伸ばさなければなりませんから、簡単な話ではありません。
体が1つの細胞からなる、単細胞生物であればとても簡単なのですが。
私でも遺伝子操作して伸ばせます(笑)
ところで、活性酸素が老化につながる話を聞いたことがあるでしょうか。
活性酸素はテロメアの短縮を早めるのではないかと言われています。
だから老化が早まるのですね。
ベニクラゲは、若返りを行ない出だすと、このテロメアも長くなります。
命の巻き戻しを行なう、大変特殊な生物ですね。
実現してしまったら、不老不死の本人は苦しむ結果になるのかもしれませんが、
「寿命」というものは科学的に解明されつつあります。
さて、ベニクラゲというクラゲがいます。
「不老」ではありませんが「不死」とは呼べるかもしれません。
一度、老化を辿りますが、死ぬ寸前に若返り始め、生まれた頃にリセットされる驚きの生物です。
もちろん、物理的に殺してしまえば死んでしまうので、完全なる不死ではありません。
私は遺伝子工学が専門ですが、この系統の人間なら寿命を決めるものは誰でも知っています。
「テロメア」と呼ばれる、染色体(DNA)の両端の部位です。
若い細胞というのは細胞分裂を盛んに行ない、新しい細胞を生み出します。
ところが、細胞分裂はどれだけでも起きる訳ではなく、限度回数があります。
この限度回数を決めているのが「テロメア」だろうと言われています。
細胞分裂を繰り返す度に、テロメアという部位は短くなっていきます。
テロメアがなくなってしまった細胞は、それ以上分裂することがなくなります。
こうなると、その細胞自身の寿命までで終わり。
あとは死に向かうしかありません。
細胞死が増えれば、体中の器官は不調をきたし、生命を維持できなくなります。
ということは、テロメアをどうにか伸ばすことができれば、細胞分裂を復活させられ、生命を維持することができるようになります。
「テロメアの長さを維持すること」が不老不死につながるのです。
といっても、体中の全ての細胞のテロメアを伸ばさなければなりませんから、簡単な話ではありません。
体が1つの細胞からなる、単細胞生物であればとても簡単なのですが。
私でも遺伝子操作して伸ばせます(笑)
ところで、活性酸素が老化につながる話を聞いたことがあるでしょうか。
活性酸素はテロメアの短縮を早めるのではないかと言われています。
だから老化が早まるのですね。
ベニクラゲは、若返りを行ない出だすと、このテロメアも長くなります。
命の巻き戻しを行なう、大変特殊な生物ですね。
落葉する理由。
2012年11月19日
この時期のけやき通りは落ち葉とのイタチごっこ。
毎朝、必死に落ち葉を掃く会社員の方を見ます。
ご苦労様です。
さて、なぜ落葉樹は冬になると葉を落とすのでしょう?
これは省エネと関係があります。
葉は食べることができない植物にとって重要なものです。
光を浴びることで光合成を行い、生命活動に必要な養分(デンプン)を作るのです。
光合成には他に水を必要とします。
葉の表皮にある気孔とよばれる穴から水を蒸発することで根から吸い上げる力を生み出します。
ストローのような感じですね。
葉で作られた養分は師管という管を通って全身に運ばれ、新しい枝葉を作るエネルギーとして使われます。
日差しが強い時期は十分な養分が得られるのでこれを繰り返せば良いのですが、
冬になると日差しは弱く、気温も低くなるため、光合成の効率が落ちてしまいます。
そこで落葉樹はエネルギーを作っては使うというサイクルをストップさせます。
葉を落とせば水の循環量が少なくなります。
新しい枝葉を作らないことでエネルギーの消費も抑えられます。
動物で言えば冬眠の始まりが「落葉」なのですね。
もう一つの理由として、自ら肥料を作り出そうとしているという見方もあります。
葉を根元に落とし、バクテリアに分解してもらって肥料を得るのです。
これは落葉樹に限りません。
常緑樹も古い葉は落とします。
よく掃除で、葉の根元まできれいサッパリ掃いてしまう人がいますが、本来植物にとっては良いことではありません。
動物も植物も、生命活動の危機となり得る越冬方法を工夫しているのです。
私たち人間はより住みやすい環境を求めるばかりに、エネルギーを使いまくりますが、
ここに来てようやく省エネにたどり着きました。
消費することと温存することの両方のバランスを上手く取ることが自然な姿なのですね。
毎朝、必死に落ち葉を掃く会社員の方を見ます。
ご苦労様です。
さて、なぜ落葉樹は冬になると葉を落とすのでしょう?
これは省エネと関係があります。
葉は食べることができない植物にとって重要なものです。
光を浴びることで光合成を行い、生命活動に必要な養分(デンプン)を作るのです。
光合成には他に水を必要とします。
葉の表皮にある気孔とよばれる穴から水を蒸発することで根から吸い上げる力を生み出します。
ストローのような感じですね。
葉で作られた養分は師管という管を通って全身に運ばれ、新しい枝葉を作るエネルギーとして使われます。
日差しが強い時期は十分な養分が得られるのでこれを繰り返せば良いのですが、
冬になると日差しは弱く、気温も低くなるため、光合成の効率が落ちてしまいます。
そこで落葉樹はエネルギーを作っては使うというサイクルをストップさせます。
葉を落とせば水の循環量が少なくなります。
新しい枝葉を作らないことでエネルギーの消費も抑えられます。
動物で言えば冬眠の始まりが「落葉」なのですね。
もう一つの理由として、自ら肥料を作り出そうとしているという見方もあります。
葉を根元に落とし、バクテリアに分解してもらって肥料を得るのです。
これは落葉樹に限りません。
常緑樹も古い葉は落とします。
よく掃除で、葉の根元まできれいサッパリ掃いてしまう人がいますが、本来植物にとっては良いことではありません。
動物も植物も、生命活動の危機となり得る越冬方法を工夫しているのです。
私たち人間はより住みやすい環境を求めるばかりに、エネルギーを使いまくりますが、
ここに来てようやく省エネにたどり着きました。
消費することと温存することの両方のバランスを上手く取ることが自然な姿なのですね。